映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」は、1969年に行われた三島由紀夫と東大全共闘の討論会から約50年を経て制作されました。
50年前の討論の映像
監督の豊島圭介氏は、ドキュメンタリーの経験がない中でこの題材を選んだ理由として、プロデューサーから「全共闘世代のことは詳しくないが、母校のことでもあり、きちんと向き合って自分たちで結論付ける作業をしてもいいのではないか」と誘われたことを挙げています。
生まれる前の話であり、一夜漬けでは分からない難しさがあると感じつつも、簡単に太刀打ちできないところに逆に魅力を感じたと述べています。制作の当初は難解な言葉に苦労したものの、この討論が今に対してどのような意味を持つのか、その答えを探すためにインタビューを行うことをテーマにしました。
この映画は、50年前の討論の映像に、50年後に関係者へ行われたインタビューを挟む構成で進行します。インタビューを受けたのは、東大全共闘のメンバー、三島由紀夫が結成した「楯の会」の会員、評論家、作家など13名です。インタビューを通して、50年前と50年後の同じ人物を比べて編集できるという点も、この映画の面白さとなります。
50年後の視点からの評価
討論会の「熱量」と「言葉の力」
討論の映像は90分残されており、その「映像」が持つ力が本作の見どころです。書籍で討論の様子を読んだ人も、映像を見ると「そういうことだったのか!」と思えるといい、文字では残せないことが残っているのが一番の魅力だとしています。
たとえば、三島由紀夫が話した時の学生の反応や、TBSのカメラマンのカメラアングルによって三島が何を見て笑っていたのかが見えるなど、「映像になっていることの意味が非常に大きい」のです。
討論の内容が抽象的で難解だと感じる人もいる一方で、その言葉には確かな「熱量」を感じる、言葉がロケットのように飛び交い、教室中に突き刺さっているようだと評する人もいます。現代のSNS上に「論破」が蔓延する中で、三島と全共闘の「対話」から学ぶべき言葉の重みがあるのです。
討論者たちの「敬意」
思想的には正反対の立場でありながら、討論会では時にユーモアを交え、相手の話を最後まで聞いてから発言する三島の態度が好印象だったと関係者は振り返ります。内田樹氏は、三島が1000人を「誠実に説得させようとしている」、相手を困らせたり追い詰めたり論理矛盾を指摘したりすることが一度もないと述べており、現代の「論破」とは異なると評価しています。
討論会では白熱した言葉が交わされますが、誰も相手を馬鹿にすることはなく、互いに敬意を持って言葉を尽くす雰囲気です。芥正彦氏も、討論では自身の主張は譲らなかったものの、笑みを交えたり三島のタバコに火をつけたりする場面もあり、完全な敵味方というよりはライバルに近い関係性だったのではないかとして、「憎しみあっていれば口もきかない」と語っています。討論会を振り返って三島は、「大変愉快な時間だった」と語っていたそうです。
共通の敵と方法論の違い
イデオロギー的に対立する三島と全共闘ですが、実は共通の敵がいることが議論を通して分かってきます。その一つとして「反米」ナショナリズムが挙げられており、全共闘は日米安保条約に猛烈に反発し、内田樹氏は全共闘を「反米愛国運動」であったと分析しています。
三島と全共闘は同じ敵と対峙しながらも、三島は「天皇」という拠り所にこだわり、全共闘はそれを支持できない点で、方法論の根本部分で相容れなかったとされています。
「持続」の問題
全共闘が「権力からの解放」を目指すのに対し、三島は「天皇」という「名付け」にこだわりました。三島が「名付け」や「持続」にこだわるのは、革命を叫ぶだけでは拠り所がなく空中分解してしまうことを危惧していたからであり、この点では三島の方が「リアリスト」だという見方も出来ます。
三島が拠り所とした「天皇」は、「昭和天皇」その人ではなく、日本の民衆の底辺に流れるエネルギーの源泉としての、もっと崇高な概念としての「天皇」だったと分析されています。三島は自身が「日本人」であること、「天皇」という概念を拠り所にすることを自身の宿命と信じていると語っています。
当時の時代背景と影響
討論が行われたのは、東大安田講堂事件のバリケード封鎖が解除された後、東大全共闘の運動がいったんフェードアウトしかけた時期であり、安田講堂に立てこもっていたメンバーとは毛色の違うメンバーが、「文化闘争でもう一旗揚げよう」と企画した背景があったと分析されています。
討論会終了後、三島は「言葉は言葉を呼んで、翼をもってこの部屋の中を飛び回った」「この言霊がどっかにどんな風に残るか知りませんが、その言葉を、言霊を、とにかくここに残して私は去っていきます」と述べています。そして、「諸君の熱情は信じます。これだけは信じます。他のものは一切信じないとしても、これだけは信じる」と学生に語りかけました。
三島事件との関連
討論会から約1年半後に、三島は市ヶ谷駐屯地で割腹自殺を遂げます。
豊島監督は、三島の自決という途方もない大きさに触れつつ、全共闘との討論会で「生き生きと輝いている映像があり、このとき、三島由紀夫はどういう状況だったのか?ということを辿っていく行為であればドキュメンタリー制作ができる」と考えた、そう振り返っています。
討論で三島が「歴史にやられたい」と語ったことに、この時すでに自らの死が念頭にあったのかを問いかけます。三島はノーベル文学賞候補にも選ばれるほどの世界的に評価の高い作家でありながら、自衛隊駐屯地に乗り込んで切腹したことは、当時の人々にとって非現実的で理解し難い状況でした。
三島事件は、多くの新聞社説や海外報道で「狂気」と捉えられましたが、一方でその行動は「社会的政治的な行為」であり、彼の文学と政治的現実の痛ましい接点、観念と肉体の破滅的な合致があったという見方や、「狂い死に」の伝統を連想させるという見方もあります。
死を賭けた三島の言葉は、多くの人々に衝撃を与えました。事件から50年後、三島と「交通事故のように出会ったことで人生を規定されてしまった」人たちがいると、監督は感じています。たとえば全共闘の芥正彦氏は今も三島を批判しつつ、三島と討論したことは彼の中の大きなアイデンティティーの一つだろうと監督は推察しています。
三島が文学サイドから政治へのコミット、文学の革命が社会の革命になることを信じていた可能性や、彼の死が日本の近現代史における「国民的苦悩」の表出であったという見解もあります。
世代への影響
討論会や三島事件が、当時の若者やその後の世代に与えた影響についても言及されています。数学者であり思想家の岡潔氏は、三島の行動は当時の日本に対する憂いや、「天皇」の重要性からの行動であったと指摘します。割腹自殺をもってそれを示しているのは勇気が必要なことであり、「本当に偉い人だと思います」と評価し、西洋かぶれした人々の見方が間違っていると述べています。
安保闘争が終わり、東アジア反日武装戦線のメンバーとなった齋藤和という人物が、三島の死に影響を受けて自殺したと解釈する見方もあります。東大闘争を経験した世代の中には、当時の暴力を目の当たりにした経験から、非暴力の姿勢を教師生活に還元し、民主主義教育をどう発展させるかという「宿題」を解き続けている人もいます。
三島由紀夫という人物像
映画の制作を通して監督は、三島を「多面体のような不思議な人」と感じています。文豪、右翼といったイメージだけでなく、ユーモアがあり、格好良く、面白く、人間味があったという元担当編集者の視点も紹介されています。
全共闘にも楯の会にも、そして担当編集者にも本気で向き合う三島の姿から、誰に対しても本気で芝居をしているような、多面的な魅力を持つ人物。三島は文学作品を通じて自己表現を追求しましたが、同時に現実の社会に影響を与えうる「言葉の有効性」を問い続けた人物なのです。

残されたフィルムでは1,000人の学生対三島1人の構図ですが、50年後のこの映像においても、制作した側、コメントや証言する者ほぼ全てが左翼思想の人々であり、三島とは異なる立場にあります。
死してなお、三島由紀夫は彼らに映像を通してただ一人の論争を挑み、「言葉」を持って彼らを圧倒してしまいます。その点に限れば、三島は「天才」と呼ぶより「超人」とでも称した方が、相応しいように感じます。
それほどの人物にも関わらず、三島事件が奇異(狂気)に映るのは、「言葉」と「行動」を隔てるあまりに大きな乖離を感じさせるからでしょうか。自らの死をもって意志や理念を体現するというより、強烈な「美意識」のなせる技であった気がしてなりません。
「日本」も「天皇」も、「自衛隊」も「特攻隊」も、そして自らの最後も、総ては三島が己に課した美学にもとづき、実現されなければならなかったのです。
不毛な日常や現実を忌避し、理想とする美に殉じたと考えれば、割腹という行動にも合点がいきます。
三島が提示した思想は日本的「右翼」かもしれませんが、根底にあるのはゲーテやワーグナーのような、ヨーロッパ型ロマン主義だったかもしれません。
それにしても彼の弁舌の、なんと魅力的なことでしょうか!


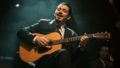
コメント