映画「駅 STATION」は、1981年に公開された高倉健さん主演の刑事ドラマです。北海道の雄大な自然を背景に、殺人事件を追う刑事の孤独な旅路と、様々な人々との出会いを描いた名作として知られています。
『駅 STATION』 時を超えて交差する3つの物語
三つの時代を背景にして、刑事・三上英次(高倉健)と、三人の女性との出会いから別れが描かれます。それぞれの時代、それぞれの場所で英次は事件と向き合いながら、自身の生き方をも見つめ直していきます。以下、時代ごとに分けてあらすじを再構成しました。
1968年 銭函駅- 妻・直子との別れ
降りしきる雪の中、銭函駅で妻の直子(いしだあゆみ)と息子・義高と別れる英次。オリンピック射撃選手として多忙な日々を送る直子との間には、深い溝ができていました。この別れは英次にとって、孤独な旅の始まりを意味していました。
直後、上司である相馬(大滝秀治)が、連続警察官射殺犯・森岡(室田日出男)に射殺されるという事件が発生。英次は犯人追跡を願い出ますが、却下されてしまいます。同時期に起きたマラソン選手・円谷幸吉の自殺のニュースが、英次の心に重くのしかかります。
1976年 増毛駅 – すず子との出会い、そして兄の逮捕
妹・冬子(古手川祐子)の結婚に複雑な思いを抱える英次。オリンピック強化コーチをしながら、赤いミニスカートの女を狙う通り魔事件を追っていました。捜査線上に浮かんだのは、増毛駅前の食堂で働くすず子(烏丸せつこ)の兄・五郎(根津甚八)です。コーチを解任され失意の中、すず子を尾行する英次。すず子はチンピラの雪夫(宇崎竜童)に弄ばれながらも、彼を兄に会わせようと五郎の潜伏先に案内します。そして英次が五郎と対峙した時、待ち伏せていた警官隊が現れ、五郎は逮捕されました。すず子の悲痛な叫びが、英次の心に深く突き刺さります。
1979年 増毛駅、そして留萌るもい – 桐子との出会い、そして別れ
五郎から刑の執行を知らせる手紙を受け取った英次は、警察官を辞める決意を固め、故郷・雄冬へ帰る道すがら増毛駅に降り立ちます。連絡船の欠航で足止めされた英次は、小さな居酒屋「桐子」で女店主の桐子(倍賞千恵子)と出会います。孤独な者同士、二人は惹かれ合い、大晦日には一緒に映画を見に行きます。
束の間の幸せを過ごした二人でしたが、元旦、英次は桐子を見つめる男に気づきます。その男は指名手配犯の森岡でした。かつて英次の上司を射殺した逃亡犯と、11年の時を経て巡り会ったことに後から気づくのです。
雄冬から戻った英次は、駅で見た指名手配の写真と桐子を見つめていた男の顔が、頭の中で完全に一致しました。すぐさま桐子のアパートに駆けつけそこに潜伏していた森岡と対峙、銃を抜いた森岡を射殺します。
森岡をかくまっていた桐子。札幌へ戻る英次は、桐子に別れを告げます。「舟唄」を聴きながら涙を流す桐子。英次は辞職願を破り捨て、列車に乗り込みます。同じ列車には、札幌で働くことを決意したすず子の姿もありました。
それぞれの女性との出会いと別れを通して、英次は人生の悲哀と希望を経験します。三つの駅を舞台に繰り広げられる人間ドラマは、観る者の心に深く響きます。
主要な登場人物たち
英次は家族との別れ、犯罪者との対峙、そして新たな出会いを通じて成長していきます。直子、すず子、桐子という三人の女性との関係が、物語の重要な軸となっています。特に「舟唄」が流れるシーンでは、それぞれの関係性が印象的に描かれています。
高倉健が演じる寡黙な刑事 三上英次
主演の高倉健さんは、寡黙でストイックな刑事、三上英次を演じています。セリフは少ないながらも表情や佇まいで、英次の心の機微を見事に表現しています。北海道の広大な風景の中で、孤独な男の背中が物語に深みを与えています。
個性豊かな3人の女性
いしだあゆみ 英次の元妻・直子を演じました。オリンピック選手としての夢と、妻としての役割の間で揺れ動く複雑な心情を繊細に表現しています。冒頭の別れのシーンは、短いながらも強い印象を残しました。
倍賞千恵子 留萌の居酒屋の女主人・桐子を演じました。人生の苦労を背負いながらも、明るく前向きに生きる桐子の姿を、温かくも切なく演じています。高倉さんとの共演シーンは、静かながらも深い情感に満ちています。
烏丸せつこ 兄を慕う純粋な女性・すず子を演じました。厳しい境遇の中でも健気に生きる姿は、観る者の心を掴みます。事件に巻き込まれ、悲劇的な運命を辿る姿は、物語に重みを与えています。
制作陣のこだわり
企画 – 脚本家倉本聰の構想
「駅 STATION」の企画・脚本は、数々の名作ドラマを生み出した倉本聰さんが手掛けています。北海道出身の倉本さんは、故郷の風景を舞台に、人間の生き様を描きたいという強い思いを持っていました。そして、旅を続ける刑事という設定を思いつき、そこから物語が生まれたそうです。
監督 – 降旗康男の演出
「駅 STATION」の監督は、降旗康男さんが務めました。高倉健さんとは数々の作品でタッグを組んでおり、互いの信頼関係は非常に厚いものでした。降旗監督は俳優の演技を引き出す手腕に長けており、高倉健さんの寡黙な演技の中に潜む感情の機微を、見事に捉えています。
宇崎竜童 – 情感をかき立てるメロディー
音楽を担当したのは、宇崎竜童さんです。彼の作曲したテーマ曲は、映画の雰囲気と見事に調和し、物語の情感をさらに深めています。哀愁を帯びたメロディーは、主人公の孤独や人々との出会いの温かさを際立たせ、観る者の心を捉えます。第5回日本アカデミー賞では、自らも出演したこの作品の助演男優賞にノミネートされ(優秀賞)、最優秀音楽賞を受賞しています。
時代を映す風景
1968年から1979年という時代の流れの中で、変わりゆく日本の姿も背景として描かれています。日本では戦後1955〜73年の約20年にわたり,経済成長率(実質)年平均10%前後の高い水準で成長を続けました。
1968年といえば、日本はいざなぎ景気と呼ばれ57か月間続いた高度経済成長時代のさ中にありました。前年には国民所得倍増計画を達成し、この年には国民総生産(GNP)が西ドイツを抜き、アメリカに次ぐ世界第2位の経済大国となります。
1973年になると、固定相場制が変動相場制に移行します。石油危機に世界経済は大打撃を受け、日本も異常な物価の高騰(狂乱物価)に苦しみ、高度経済成長は終わりを告げました。1974年に戦後初めて経済成長率がマイナスに転落し、1979年以降で石油危機や円高による不況を乗り切り,安定成長時代をむかえています。
映画では、東京オリンピックの影響や地方都市の様子など、時代性を感じさせる描写が随所に見られます。
「これは『舟唄』という映画なんです」
「駅 STATION」で印象的に使用されている「舟唄」ですが、実は当初、劇中歌として使用する予定はありませんでした。撮影現場で偶然ラジオから流れてきた「舟唄」を聴いた高倉健さんが、その曲の持つ哀愁漂うメロディーに心を打たれ、監督に提案したことで採用が決まったと言われています。
その後、高倉健さんは八代亜紀さんと対談する機会があり、「これは『舟唄』という映画なんです」と語ったエピソードが残っています。この言葉からも、高倉健さんが「舟唄」にどれほど感銘を受け、映画にとって重要な要素だと考えていたかが分かります。
北海道の雄大なロケーション
各地の「駅」が舞台装置として重要な役割を果たす
映画のタイトルにもなっている「駅」は、単なる場所ではなく、物語の重要な要素となっています。人々が行き交い、出会い、別れ、そして新たな旅立ちが始まる場所。それぞれの「駅」が、登場人物たちの心情を映し出す舞台装置として機能しています。釧路駅、小樽駅、札幌駅、それぞれの駅が持つ独特の雰囲気が、物語に深みを与えている点も見逃せません。
釧路湿原での撮影秘話
「駅 STATION」の冒頭、釧路湿原を走るSLのシーンは、映画史に残る名シーンの一つです。このシーンの撮影は、非常に困難を極めたと言われています。広大な湿原での撮影は天候に左右されやすく、何度もの撮り直しを余儀なくされたそうです。完璧な映像を追求する制作陣のこだわりが、あの美しいシーンを生み出したのです。
小樽運河の幻想的な風景
小樽を舞台にしたシーンでは、小樽運河の幻想的な風景が印象的です。ガス灯に照らされた運河沿いを歩く高倉健さんの姿は、どこかメランコリックな雰囲気を醸し出し、物語の切なさを際立たせています。
「駅」の深い象徴性
出会いと別れの場所
駅は人々が行き交う場所、出会いと別れが交差する場所です。映画の中でも英次はそれぞれの駅で様々な人物と出会い、そして別れていきます。妻の直子、すず子、桐子、そして故郷の友人たち。駅での出会いと別れは英次の人生における転換点となり、彼の孤独を際立たせると同時に、人との繋がりを暗示しています。
旅の起点と終点
駅は旅の始まりであり、終わりでもあります。英次にとって駅は事件を追う旅の起点であり、故郷へ帰る場所でもあります。彼の旅は物理的な移動だけでなく、心の旅路も象徴しています。私たちは人生という長い旅路の中で、様々な「駅」に立ち寄り、人々と出会い、別れを経験します。それぞれの駅で経験する出来事は人生における通過点となり、英次の成長を促していくのです。
時間の流れ
駅は常に人々が行き交い、時間の流れを感じさせる場所です。映画では三つの異なる時代が描かれていますが、それぞれの時代の「駅」は時代の変化と時間の流れを象徴しています。変わっていく風景、そして変わらぬ人々の営み。駅はその両方を映し出す、鏡のような存在なのです。
逃れられない運命
駅は定められた路線に沿って列車が運行されるように、逃れられない運命を象徴しています。英次は刑事として事件を追う中で、様々な運命に翻弄されます。彼自身もまた、自身の運命を受け入れ、生きていくしかありません。駅はそんな人間の無力さと、それでも生きていく強さを象徴しているのかもしれません。
希望と再生
駅は新たな目的地への出発点でもあり、希望と再生を象徴する場所でもあります。映画のラストシーンで英次は辞職願を破り捨て、列車に乗り込みます。これは彼が過去を乗り越え、新たな人生へと踏み出す決意を表していると言えるでしょう。駅は彼にとって、再生の場所となったのです。
「駅 STATION」における「駅」は、多層的な意味を持つ象徴的な存在です。観る人それぞれが自身の経験や感情と重ね合わせ、異なる解釈をすることができるでしょう。それこそがこの映画の、最大の魅力なのです。

高倉健さんはその時々の役柄を演じると同時に、生涯「高倉健」を演じました。観るもの(男)誰もを「高倉健」に転写してしまうことまで含めると、二重三重にも重ねた分厚い演技をしていたことになります。
「駅」の主人公は常に目標とした夢に破れ、現実にくじけそうになる敗者の論理を背負っています。それを「高倉健」が演じれば、悲壮感など微塵もなく、何をやってもいつもの「健さん」になってしまいます。こんな俳優さん、他に思い浮かびません。
ネットもスマホもない昭和の時代だから可能だったのかもしれませんし、後になれば多少の裏話も出てきたりはしました。それでも人の目のあるところでは、徹底して「高倉健」を演じきった役者魂に畏敬の念を抱きます。
健さんから「これは『舟唄』という映画なんです」なんて言われたら、いくら天下の八代亜紀さんであっても、きっとイチコロだったことでしょうね。

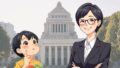
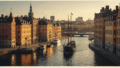
コメント