1955年2月12日、日本映画史に新たな名作が誕生しました。その名は「ここに泉あり」。
終戦直後の混沌と貧困の時代、群馬県高崎市で産声を上げた群馬フィルハーモニーオーケストラ(現・群馬交響楽団)の知られざる苦難と、そこから希望を紡ぎ出した人々の魂の物語です。
今井正監督と水木洋子脚本のタッグによって生み出された本作は、当時としては異例の独立プロ作品でありながら、なんと全国で300万人を超える大ヒットを記録しました。
荒廃した戦後の日本において、音楽がいかに人々の心に希望と喜びをもたらす力となり得たか、そして夢と現実の間で葛藤しながらもひたむきに音楽の道を追求した人々の情熱が、鮮やかに、生々しく描き出されています。
第1章:瓦礫の中のハーモニー/市民フィルハーモニーの誕生と最初の試練
昭和21年の春、終戦直後の日本はまだ深い傷跡と貧困にあえいでいました。そんな中でも人々の心を音楽で活気づけようと、群馬県高崎市に「市民フィルハーモニー」(後に高崎市民フィルハーモニーオーケストラとも呼ばれる)が誕生します。
楽団のマネージャーを務める井田亀夫(小林桂樹)は、この楽団をプロのオーケストラに育て上げるべく一計を案じます。彼が白羽の矢を立てたのは、東京からやってきた気鋭のヴァイオリニスト、速水明(岡田英次)でした。速水をコンサートマスターとして招き入れた井田の心には、楽団の未来への確固たる信念がありました。
しかし速水が目の当たりにしたのは、想像以上に低い楽団の演奏レベルでした。彼は一度は絶望し置き手紙を残して去ろうとしますが、井田の巧みな計略により引き留められます。
そんな速水の心を動かしたのは、楽団で唯一の女性団員であるピアニストの佐川かの子(岸恵子)でした。音楽学校を出たばかりのかの子は、田舎にいることでピアノの腕が落ちることを人知れず悩んでいました。ひたむきに練習を続ける彼女の姿に、速水は楽団に残ることを決意し、温かく励ますのでした。
速水は楽団員に厳格な練習への完全参加を求めます。
その結果、本業の傍らで音楽活動をしていた古参の団員の多くが楽団を去ってしまいます。元軍楽隊出身の工藤(加東大介)や丸屋(三井弘次)らが残りましたが、最終的に楽団はマネージャーを含めて、わずか7人にまで減ってしまいます。
彼らが次の公演に向かう日、土砂降りの雨が降り注ぎ、観客のほとんどは音楽に耳を傾けずに帰ってしまいました。落胆して引き返す楽団員の前に、校門の陰で待っていた一人の少女がかの子に、野の花で作った花束を差し出します。この少女は後に文学座で活躍する、寺田路恵とされています。
この純粋な歓迎に楽団員たちは、「来てよかった。あんな子が一人でもいてくれるなら、どんなに遠くでも行く」と心から感動し、満たされた心で「美しき青きドナウ」を口ずさみながら帰路につきます。
このシーンは演奏する側の、「なぜ演奏するのか?活動を続けるのか?」という根源的な問いへの答えであると評されています。
第2章:人生のハーモニー/結婚、プロとの邂逅、そして「音のない拍手」
その後、速水とかの子は人生の伴侶となり、かの子は新たな命を身籠もります。
楽団の活動も軌道に乗り始め、ついには作曲家の山田耕筰(特別出演)指揮の交響楽団と、高名なピアニストの室井摩耶子(特別出演)を東京から招き、合同演奏会を開催する運びとなります。かつての楽団員たちも協力し演奏会は大盛況に終わりますが、経営は依然として赤字でした。
かの子は室井摩耶子の卓越した演奏を目の当たりにし、自身の技術が遅れをとっていると感じ、プロとの差に焦りを抱きます。
一部の団員も同様に実力の差を痛感し、音楽の道をさらに深く学ぶために楽団を去っていく者もいました。
楽団は再び巡回公演に出かけます。彼らが草津にあるハンセン病療養所(栗生楽泉園)を訪れた際に、特別な感動が待っていました。
患者たちは皆、真剣に音楽に耳を傾け、彼らが不自由な手で拍手をするその音は、「音にならない拍手」でした。
楽団員たちはその演奏会を「最高の演奏会」と感じます。ハンセン病は手足など末端の神経症状が麻痺する病気であり、患者たちは麻痺した手で精一杯の拍手を送っていたのです。
患者代表は療養所への訪問に深く感謝し、「私たち、永劫に救われることのない世界にいる者が、皆さんの訪れをどんなに待ち望んだか、想像もつかぬことと思います。今日こそ感じるであろう、生きている喜びは一生消えることはありません」と挨拶を述べます。
このハンセン病療養所の描写については、後に「差別的」であるとの指摘や「戦後民主主義の限界」という見方も示されます。
患者会から修正を求められた部分(例えば「未来永劫に救われることのない」という台詞)も、当時の社会情勢と向き合う上で重要なシーンであったことは間違いありません。
ちょうどその頃、かの子は難産で苦しみますが、速水たちが戻ってきた時に二人の最初の子供が生まれます。患者の悲しみに触れた夜に新しい生命が誕生するという対比的な構成は、この映画にさらなる深みを与えています。
第3章:崩壊の序曲、そして利根の山奥での「最後の」演奏会
速水は子供たちの音楽的才能を育むため、楽団の練習場で子供たちにヴァイオリンを教え始めます。しかし楽団の経営はさらに厳しくなり、ついに練習場を追い出される事態に陥ります。工藤や丸屋はチンドン屋として日銭を稼ぎ、井田は家を担保に入れて楽団を支えますが、井田の妻(千石規子)は激しい夫婦喧嘩の末、娘を連れて家を出ていきます。
ピアノまで売却せざるを得ない状況となり、楽団員たちは会議を開きます。その席で丸屋が仲間の楽器を質に入れていたことが発覚し、激しい喧嘩に発展します。楽団は解散することを決定しますが、既に決まっていた最後の公演だけは、皆で力を合わせてやり遂げようと誓います。
楽団員たちは利根の山奥にある小学校へと向かいます。かの子も赤ん坊を背負って参加しました。聴衆は山奥の分教場から集まった、純粋な眼差しの子供たちでした。井田は子供たち一人ひとりに語りかけるように、楽器を丁寧に紹介していきます。
-
バイオリン:楽器の女王様、美しい音色を持つ。山に咲く花のように、音もそれぞれ美しい特徴を持つ。
-
ビオラ:バイオリンのお兄さんで、少し音が低い。
-
チェロ(セロ):バイオリンのお父さん。男らしく力強く、頼もしい音を出す。管弦楽にはなくてはならない楽器。
-
コントラバス:おじいちゃん。主に低音を受け持つ。
-
ホルン:虫(でんでん虫)のような形。自然音を出し、非常に弱い音から強い音まで出せるが、演奏は非常に難しい。
-
トランペット:軍隊ラッパを綺麗にした音で、管弦楽には必ず入る。
-
ピアノ:楽器の王様。一人で管弦楽の代理をする大きな力を持つ。
子供たちは真剣な眼差しで楽器を見つめ、素晴らしい演奏会となりました。最後に楽団員たちは子供たちの合唱と共に童謡「赤とんぼ」を演奏し、深く感動的な別れとなります。井田はこれらの子供たちが「もう生のオーケストラを聴くことは二度とないだろう」「みんな炭焼き夫で一生を終えるのだ」と語り、当時の地方の厳しい現実が痛切に映し出されるのでした。
第4章:奇跡の再起/そして「第九」が響き渡る高崎
それから二年後。
旅の途中にあった山田耕筰は、次の停車駅が高崎であるというアナウンスを聞き、数年前の合同演奏会を思い出します。
高崎の楽団がどうなったのか気になり、「潰れたと聞いている」という同行者の言葉にもかかわらず、高崎で途中下車します。
そこで山田が目の当たりにしたのは、信じられない光景でした。
新しい練習場で速水の指導のもと活動を続けていた「高崎市民フィルハーモニー」があったのです。
工藤や丸屋も楽団に残り、団員の数も増え、その演奏水準の高さに山田は感銘を受けます。山田はその場で指揮を執り、再び合同演奏会が開催されることが決定しました。
演奏会当日。
ベートーヴェンの第九交響曲が演奏される中、草創期の団員たちはこれまでの苦難に満ちた巡回公演の道のりを思い返し、溢れる涙を抑えることができません。
かの子は赤ん坊を背負い、人々の心に美しい音楽を届け続けるために、これからも歩き続けるのです。
映画は、困難を乗り越えて音楽を伝え続けた彼らの活動が未来へ続いていくことを示唆し、心に響くラストを迎えます。
第5章:映画と現実の交錯/群響の精神と作品の不変の意義
この映画は終戦直後の混乱と貧困の中で、地方にクラシック音楽を広めようと奮闘した人々の姿を、葛藤や困難、そして音楽がもたらす喜びと共に、生々しく、前向きに描いています。
群馬交響楽団は映画で描かれた精神を受け継ぎ、今も移動音楽教室を継続しており、小中学校や高校で演奏活動を行っています。これは、映画で描かれた楽団の活動が現代にまで受け継がれていることを示しています。
映画の公開翌年には、文部省から群馬県が全国初の「音楽モデル県」に指定されるきっかけとなりました。
しかし、映画と現実の間にはいくつかの乖離もあります。全編の演奏は当初、群馬交響楽団が担当する予定でした。監督の今井正が東京交響楽団に変更を決め、群馬交響楽団の演奏は使われませんでした。
このことについて当時の群響楽団員は、「プロの音楽家としてこれ以上ない屈辱であった」と語っています。
映画完成後にはスタッフから、「お前ら楽団が解散する前に映画になってよかったな」と皮肉を言われたエピソードも残っており、現実の厳しさも伝わってきます。
映画は当時の社会情勢をリアルに描いており、高崎駅構内や喫茶ラ・メーゾン(群響の練習場だった)の様子、破れた障子のある住宅、衿の汚れたシャツなど、CGやVFXでは表現できない「重み」や「匂い」が感じられると高く評価されています。
榛名の久留馬小学校の校門の門柱など、ロケ地の一部が現在も残っているのはそのリアルさの証とも言えるでしょう。
作品のタイトル「ここに泉あり」は、哲学者ニーチェの「汝の立つ処深く掘れ、そこに必ず泉あり」という言葉に由来すると言われています。この言葉は、自分の足元を深く掘り下げれば、そこに必ず泉があるというメッセージを含んでいます。
映画は地方という困難な環境で音楽の理想を追い求めた人々の姿を通じて、この言葉の意義を私たちに問いかけています。
「ここに泉あり」は第29回キネマ旬報ベスト・テンで第5位を獲得し、小林桂樹が毎日映画コンクールで助演男優賞、加東大介がブルーリボン賞で助演男優賞を受賞するなど、高い評価を得ました。岸恵子にとって音楽一筋に人生をかけるという役柄はこれが唯一であり、彼女の演技力の深みを増した名作と評されています。
この映画は音楽が持つ普遍的な力とそれを信じて奮闘した人々の物語を通じて、「音楽は誰の為のものでも無い。みんなのもの」というメッセージを伝えています。現代において地方オーケストラ運営は依然として多くの課題を抱えていますが、「ここに泉あり」は文化を創造し、守り育てることの重要性を私たちに問いかけ続ける不朽の作品と言えるでしょう。
この映画からあなたの心には、どんな「泉」が湧きだすでしょうか?

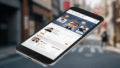

コメント