ジャズの世界にはその才能と功績にもかかわらず、広く知られることなく、あるいは正当な評価を得られずにいた「隠れた巨人」たちが存在します。トランペット奏者のウディ・ショウもまた、その一人だと言えるでしょう。
彼の「ハードボイルド」と形容されるサウンドと、ジャズの常識を覆す革新的な演奏は、現代ジャズに計り知れない影響を与え確かな「軌跡」を残しました。
この記事ではウディ・ショウという稀代のトランペット奏者が、いかにしてジャズの歴史に名を刻み、なぜ「過小評価された伝説」と呼ばれながら今なお多くのミュージシャンやリスナーを魅了し続けているのかを解説していきます。
ウディ・ショウ 孤高のトランペット奏者の誕生
ウディ・ショウは1944年、アメリカのニュージャージー州ニューアークで生まれました。18歳で初レコーディングを経験し、そのキャリアをスタートさせます。
彼の音楽的なルーツはジャズの巨匠ルイ・アームストロング、それにクラシック・トランペットの要素もあると、彼自身が語っています。
異なる2つの分野を並行して学び、トランペットという楽器が持つ神秘的な魅力を追求したのです。
1960年代後半から1970年代にかけて、ウディ・ショウはフレディ・ハバードと並ぶ実力派トランペッターとして注目を集めます。しかし、日本ではなぜか彼の人気は今一つで、「フレディ・ハバードのコピー」などと揶揄されることもありました。
彼の演奏を深く聴き込んだ人々は、ショウが誰かの模倣者でないことを知っています。彼はそれまでにない新しい響き、新しいフレーズ、そしてモードを取り入れた演奏で、ジャズに新たな地平を切り開いたのです。
革新的な演奏スタイル その「狂気」と「哲学」
ウディ・ショウの演奏スタイルは、その複雑さと鋭さに特徴があります。彼は「ハードバップからアバンギャルドまで」あらゆるスタイルに適応する卓越したテクニックを持っていました。特に注目すべきは、モードを基調とした演奏と、サイドスリッピングと呼ばれる独自のテクニックです。
彼の演奏スタイルは非常に現代的であり、楽譜に書かれたコード進行を頻繁に別のハーモニーに置き換え、それまであまり用いられなかった「色彩」を表現しました。
これは「サイドスリッピング」と呼ばれる、スケールパターンをキーの半音上または半音下で繰り返した後、元のキーに戻るというユニークなテクニックに代表されます。これにより彼のソロは、聴き手に予測不能な緊張感と解放感をもたらしました。
また彼は「長いフレーズの後に長めの休符を入れる」という特徴的なフレージングを用い、この休符自体を自身のフレーズの一部としていました。
独自の拍子記号で作曲・演奏したり、東洋音楽の要素を取り入れたり、さらには電子エフェクトを試したりと、常に実験的なアプローチも怠りませんでした。
このようなプレイは従来のジャズの枠を超えた深みと予測不能な展開をもたらし、リスナーに強い印象を与えます。
1970年代は多くのミュージシャンが、クロスオーバーやフュージョンといったポップなジャズへと傾倒していった時代です。
しかしウディ・ショウはあえてメインストリーム・ジャズを貫き、伝統に根ざした熱いジャズプレイで聴衆を魅了しました。
彼はマイルス・デイヴィスやディジー・ガレスピーのような先人たちが築いたトランペット演奏の発展において、自らが「新旧のギャップを埋める存在」であると考えていました。
彼の音楽は単なるビバップの復古でなく、「限りなく自由度の高いモーダルな演奏」と「限りなく調性に近い無調性のフリーな演奏」の両方に対応する、ハードでメカニカルなフレーズが特徴です。
ショウは精神的なバランスを保つためにも、ビバップを演奏することに再び興味を持つようになります。ジャズプレイヤーであれば「スイングの仕方を知らなければならない」という基本を大切にし、自身の演奏では常にその点に注意を払っていたのです。
ジャズ史に残る名盤たち 軌跡をたどる旅
ウディ・ショウは多くの優れた作品を残しています。その中でも特に、彼の名をジャズ史に刻んだ代表作をいくつかご紹介しましょう。
デビュー作『ブラックストーン・レガシー』
『ブラックストーン・レガシー』はウディ・ショウがリーダーとして初めてレコーディングしたアルバムです。1971年に発表されます。当時25歳であったショウにとって、音楽的ビジョンを提示する重要な作品となりました。
このアルバムには、ベニー・モーピン(テナーサックス)、ロン・カーター(ベース)、ジョージ・ケーブルス(ピアノ)、ゲイリー・バーツ(アルトサックス)、クリント・ヒューストン(ベース)、レニー・ホワイト(ドラムス)といった名だたるミュージシャンが参加しています。
演奏は正統的かつアコースティックなサウンドが特徴であり、当時のフュージョン全盛期において安易なロック・ポップ調のスタイルには流されず、「ハードエッジ」で「ストレートアヘッド」なジャズを貫くショウの姿勢が明確に示されています。
『ブラックストーン・レガシー』は、ショウの「圧倒的な音圧と溢れ出るブラック・スピリチュアリティ」に満ちています。単なるジャズの枠を超え、ワールドミュージックやクラシックの音楽体験にも似た感動を与えるような、パワフルで芳醇なサウンドを生み出しているのです。
このアルバムは、彼のプレイの中心にあるポリリズム的かつポリトーン的な要素を際立たせており、ハード・バップからアバンギャルドまでを股にかける彼の先鋭的なスタイルを象徴する一枚となっています。
特にタイトル曲「Blackstone Legacy」はポリリズム的な設定の中で、ショウ自身とゲイリー・バーツのソロが圧巻と評価されています。
アルバムには「New World」「Beyond the Red Star」「Organ Grinder」「The Moontrane」「Lito」といった楽曲が収録されており、このうち「Beyond the Red Star」は強固なハード・バップの要素を持ち、スティーヴ・トゥーレのトロンボーンソロが際立っています。
さらに注目すべき点として、アルバム中3曲目と4曲目にはジョー・ヘンダーソンの作曲した楽曲が含まれていますが、ジョー・ヘンダーソン自身は本作の演奏に参加していません。
ウディ・ショウは1962年に18歳でエリック・ドルフィーとの初レコーディングを経験して以来、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズやホレス・シルヴァー・グループといった名門バンドに参加し、ジャッキー・マクリーンやジョー・ヘンダーソン、ラリー・ヤングなど新世代の精鋭たちとも共演を重ねてきました。
彼の音楽的ルーツはルイ・アームストロングやハリー・ジェームスに強く影響を受けていますが、同時にクラシック・トランペットの学習も継続し、後にディジー・ガレスピー、ファッツ・ナバロ、クリフォード・ブラウン、リー・モーガン、フレディ・ハバードといった巨匠たちの影響を受けています。
ショウは、1970年代にジャズ・ロックやフュージョンが音楽シーンを席巻する中で伝統的なスタイルを守りつつも、ハードでアグレッシブなジャズを追求し続けました。彼はガレスピーやブラウンといった先達の音楽的遺産を受け継ぐ者として、またジャズ・メッセンジャーズの出身者として、ジャズの伝統の誠実さと評価を維持する責任を感じていました。
日本でウディ・ショウは長らくフレディ・ハバードと比較され、しばしば過小評価、不当な評価を受けてきました。
しかし確かな耳を持った一部のファンは、彼のモード・トランペットがハバードの単なる後継ではなく、マイルス・デイヴィスのモード・トランペットの延長線上からさらに先に進めた存在と主張し、再評価を強く訴えます。
彼の演奏は、高度なテクニックと豊かなイマジネーションに裏打ちされた理知的で内容の濃いモード・ジャズであり、その真価は時代を超えて聴かれるべきでしょう。
『ブラックストーン・レガシー』はウディ・ショウという比類なきトランペッターの、その後の偉大なキャリアを予見させる記念碑的な作品です。
彼の独自のアプローチとジャズの伝統への深い敬意、そして革新を恐れない精神は、このアルバムに凝縮されています。
その他のお薦め盤
1977年録音の『Rosewood』と1978年(または1979年)録音のライブ盤『Stepping Stones』は、彼の1970年代の「重厚なジャズ」を代表する傑作として評価されています。『Stepping Stones』はニューヨークの名門ジャズクラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」での熱演を収録した作品で、ブルーノート新主流派の精神をダイレクトに受け継ぐ、迫力ある演奏が楽しめます。
一方で、1977年のアルバム『The Iron Men』は、アンソニー・ブラクストンなどの参加により、より前衛的な側面を見せた作品です。このアルバムに対する評価は二分されており、一部では「聴きにくい」という声もありますが、その革新性を高く評価するファンも多く、彼の挑戦的な姿勢が色濃く反映された一枚と言えるでしょう。
彼の晩年の作品としては、1987年録音の『Imagination』が挙げられます。彼の最後のリーダー作とされており、初期のハードでアグレッシブなスタイルとは異なり、オーソドックスで柔らかい、角の取れたプレイが特徴です。スタンダードナンバーが中心に選曲されており、彼の新たな音楽的境地がうかがえます。
さらに近年では、『The Tour Volume One』(1976年)、『Live Volume Two』(1976年)、『Basel 1980』、そして1981年の日本公演を収録した『Tokyo ’81』や1983年のドイツ公演を収録した『Live in Bremen 1983』など、数々の未発表ライブ音源が続々とリリースされ、彼の輝かしい功績が再評価されています。特に、ドラマーのルイス・ヘイズとの共演アルバムは、「トランペットのコルトレーン」と評されるほど、その熱量と純粋さが際立っています。
偉大なコラボレーターと残した足跡
ウディ・ショウはそのキャリアを通じて、ジャズ界の数々の巨匠たちと共演してきました。アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズ、ホレス・シルバー、ジャッキー・マクリーン、ジョー・ヘンダーソン、マッコイ・タイナー、チック・コリア、エリック・ドルフィーなど、ハードバップからアバンギャルドまで、ジャンルを超えた多くの先鋭的なミュージシャンたちとの交流は、彼の音楽性をさらに豊かにしました。
特に、ジョー・ヘンダーソンとのフロント2管による演奏は、重厚で自由に富んだモード・ジャズでありながら、軽快さも兼ね備え、難解さを感じさせません。ジョージ・ケイブルスのエレキピアノの響きも、演奏全体に良い影響を与え、彼らの音楽をより魅力的なものにしています。ウディ・ショウのソロは、常に聴き手に深い感動を与え、その音楽は「ブラック・スピリチュアリティ」と「ヒップなグルーヴ」に満ち溢れています。
受け継がれる「軌跡」と再評価への動き
ショウの人生は、1989年に地下鉄のホームからの転落事故により左腕を切断し、その数か月後に44歳で亡くなるという悲劇的な終わりを迎えました。
しかし、その短い生涯の間に残された作品群は、巨匠としての存在感を放っています。
彼の音楽的キャリアは悲劇的と捉えられがちですが、実際には「For Sure!」のような企画盤でも見事に自らを昇華させ、「楽歴が悲劇的とは思えない」と評されるほど充実したものでした。
今日、彼の息子であるウディ・ショウ3世が監督・脚本・プロデュースを手掛けたドキュメンタリー映画『Woody Shaw Beyond All Limits』が公開に向けて募金活動を行うなど、彼の功績は世界中で再評価され始めています。
ゲイリー・バーツ、デイヴィッド・ベイカー、アンソニー・ブラクストンといった多くのアーティストが彼の生涯を語り、彼の音楽が社会的な差別と闘い、トランペット演奏に革命をもたらしたことが描かれています。
ウディ・ショウは卓越した技術を持つトランペッターだっただけでなく、ジャズの根源であるスイングを大切にし、常に新しい表現を追求し続けた真の革新者です。
彼の「ハードボイルド」なサウンドとフレーズは、ジャズトランペットの歴史に深く、そして鮮やかな「軌跡」を刻んでいます。
まだ彼の音楽を聴いたことがない方も、ぜひこの機会に作品に触れてみてはいかがでしょうか。

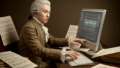

コメント