ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。
この不朽の天才音楽家は、250年以上たった今もなお、世界中の人々を魅了し続けています。彼の生み出した音楽は時代を超えて私たちの心に響き、日々の生活に彩りを与えてくれています。
もし、モーツァルトが現代に生きていたらどのような音楽を創り出し、どのような未来を私たちに見せてくれるでしょうか。
近年、目覚ましい進化を遂げるAI(人工知能)技術は、音楽の世界にも大きな変革をもたらしています。AIが作曲を行い、既存の作品を「再解釈」し、新たな音楽体験を生み出す時代が到来しているのです。
モーツァルトの古典的な音楽がAIという最先端のテクノロジーとどのように融合し、私たちの音楽の未来をどのように形作っていくのかを考察します。
モーツァルト 時代を超えて響く天才の旋律
モーツァルトはその短い生涯の中で、700曲を超える膨大な数の楽曲を創作しました。
当時の音楽家は「アーティスト」というより、「職人」に近い存在でした。速く作曲できることが重要なスキルだったと言われています。
モーツァルトもまた、「産みの苦しみの末にやっと…」というよりは、サラサラッと作品を書き上げていったのでしょう。
彼の交響曲の中で際立つのが、短調の作品です。
モーツァルトが第41番まで書き上げた交響曲の中で、短調(マイナーキー)で書かれたのは第25番と第40番のわずか2曲しかありません。どちらもト短調(G-minor)で書かれていて、第40番が「大ト短調」と呼ばれるのに対し、第25番は「小ト短調」と称され、セットで語られることもあります。
交響曲第25番の冒頭は、非常に印象的な「タタータータータ…」というフレーズで始まります。これは「シンコペーション」と呼ばれる裏拍にアクセントが来る音型で、現代のダンスミュージックにも通じる推進力と躍動感に満ちています。
もしモーツァルトが現代に生きていたら、ダンスミュージック界でも活躍していたかもしれない、と想像が膨らみます。
モーツァルトの音楽は単に聴くだけでなく、私たちの心身にも良い影響を与えると言われています。
湘南鎌倉総合病院の小林修三医師は、クラシック音楽、特にモーツァルトの音楽が心身の不調に役立つと科学的根拠に基づいて述べています。
彼の音楽は脳、特に情動を司る「大脳辺縁系」を心地よく刺激し、自律神経のバランスを整える効果が期待できるのです。薬の併用なしにうつ病を軽減したり、認知症患者の行動や認知、生理学的な指標にプラスの効果を示したりする研究結果も存在します。
これらの効果は「モーツァルト効果」として知られていますが、モーツァルトを聴けば知能指数が上がるという直接的な因果関係はまだ確立されていません。
しかし、幼少期から楽器を演奏する子供の知能指数が高い傾向にあることや、クラシック音楽を好む人を知的に感じるとの意見もあります。
日本においても多くの人が、モーツァルトの音楽に親しんでいます。音楽雑誌のアンケート調査では、好きな交響曲ランキングでモーツァルトの交響曲第41番が上位10位にランクインするなど、その人気は確固たるものです。
彼の音楽は、喜び、悲しみ、怒り、絶望といった普遍的な感情を表現し、時代や文化を超えて人々の心を動かす力を持っています。
音楽業界に訪れたAI革命 作曲の新たな地平
AI(人工知能)技術の急速な発展は私たちの生活のあらゆる側面に影響を与えていますが、音楽業界もその例外ではありません。近年、「作曲」という分野でAIの存在感が著しく増しています。
かつては人間の感性が不可欠とされていた作詞や作曲の領域において、AIが一部を担うことが可能になってきているのです。
そもそも音楽の作曲には、「スケール(音階)」「コード(和音)」「メロディ(旋律)」という3つの重要な要素があり、現代ではこれに「ジャンル」「サウンド」を加えて主に5つの要素で成り立っています。
人間が作曲を行う場合、まず音楽理論を把握し、曲のコンセプトを決め、曲調やコード進行を決定し、そこにメロディやサウンドを加えていきます。
一方、AIが自動作曲を行うプロセスはまったく異なります。
AIはまず、大量の譜面データを学習します。この学習によってAIは、コードのパターンなどを記憶するのです。
ユーザーが「曲調」のような一定の指示をAIに与えると、AIは学習したデータに基づいて作曲作業を進めていきます。作りたい曲のコンセプトが定まっていれば、AIは作曲の3要素である「スケール」「コード」「メロディ」を網羅した楽曲を生成することが可能です。
AI作曲の核となるのは「機械学習」、特に「ディープラーニング」と呼ばれる技術です。
例えばGoogleが開発した囲碁AI「AlphaGo」がトッププロに勝利したのも、機械が自ら学習を重ね、成長していった成果です。
アマゾンが発表した「AWS DeepComposer」は「Generator(演奏者)」と「Discriminator(指揮者)」という2つの機能をAIに持たせることで、AIが自ら生成したメロディやコードに対してフィードバックを行い、性能を向上させていきます。
しかし、現在のAI技術だけで「これまでにない独創的な音楽を創り上げる」ことはまだ難しいと言わざるを得ません。AIは学習した譜面パターンをもとに楽曲を生成するため、そのパターンに限定されてしまうという前提があります。
自動作曲された曲のメロディが単調になってしまうケースも少なくないため、この分野にはまだ改善の余地があると言えるでしょう。
それでもAIは作曲家をサポートする強力な存在として、今後ますます重宝される可能性を秘めています。
古典音楽とAIの融合事例「Project Z」
モーツァルトの音楽とAIテクノロジーを融合させ、彼の「新しい音楽」を生み出すという画期的なプロジェクトが2019年に発表され、大きな注目を集めました。
日本HPの協力を得て「Project Z」と名付けられたこの取り組みでは、プロのクリエイター3名と現役高校生18名が参加し、AIをはじめとする最新テクノロジーを駆使して現代にモーツァルトを蘇らせました(残念ながら、現在は非公開になっています)。

プロジェクトの出発点は、「もしモーツァルトが現代に生きていたら…」という仮説でした。
高校生たちはインターネット上からモーツァルトの既存楽曲のMIDIデータを約60曲ほど集め、AIにディープラーニングさせるところから始めました。
当初はめちゃくちゃな音程やブレたリズムの曲しか出てこなかったものの、試行錯誤を重ねる中で、メロディ部分だけを8小節や16小節といった短い単位で切り出し、約80曲ほどのストリーミングデータとして学習させると、うまくいくことが分かってきました。
学習回数も重要で、1,500回以上学習させると良い結果が出やすい一方で、3,000回を超えて学習しすぎるとかえって3音程度の単調な曲になってしまうという発見もありました。
高校生たちは日本HPから提供されたノートPCを使い、DAW(デジタルオーディオワークステーション)ソフトでMIDI編集し、GoogleのColaboratoryというツールでAIのディープラーニングを進めたそうです。
特に、ニューラルネットワークの「隠れ層」というパラメータが作曲に大きく寄与することも見出したといいます。
約2カ月にわたる高校生たちのAI作曲作業の後、完成した楽曲はプロのクリエイターへと引き継がれました。
AIが生成したメロディは、確かにモーツァルトらしさを持ちつつも突然1オクターブ飛ぶなど、そのままでは使いにくい部分もあったと作曲家の江夏正晃氏は語っています。
彼は「音符は一切触らない」という鉄則を設け、AIが作り出したものを忠実に残しつつ、切ってつなぐ形で編集を進めました。ピアノ、ベース、ドラム、シンセ、そしてヴィオラ、第1バイオリン、第2バイオリン、チェロ、コントラバスといったオーケストラの音源を重ねて曲を構成していきます。
打ち込みながらも、全て手弾きでリアルタイムレコーディングを行い、クォンタイズをかけずに「揺らぎ」を加えることで、AIが作ったカッチリとしたテンポの楽曲に人間的な温かみを吹き込んだのです。
歌詞の生成には、AIを手掛ける企業の協力も得られました。
モーツァルトの手紙を英訳したデータと、ビルボードチャートのトップ100の楽曲歌詞データをAIに学習させることで、1万ワードもの文字列から曲に合ったフレーズを生成し、これをベースに「10 Million Nights」というタイトルが付けられました。
当初は歌声合成ソフトの使用も検討されましたが、最終的には人が歌うことで、より雰囲気のある楽曲が完成しました。
「Project Z」は音楽制作だけに留まりませんでした。
このプロジェクトでは完成したAI楽曲に合わせて、最先端の映像やオーディオが融合されたのです。
8Kカメラで撮影されたバレエダンサーの映像に、インタラクションデザイナーがリアルタイムで画像処理を施し、粒子やエフェクトが映像に反応する仕組みを構築します。
会場に設置されたカメラの映像もリアルタイムで処理することで、来場者自身が映像に映り込み、リアルタイムレンダリングを実感できる体験を提供しました。
12.1chの立体的なイマーシブサウンドシステムも導入され、まさに「現代に蘇ったモーツァルト」の音楽を五感で感じられるような空間が作り出されました。
このようなAIと人間の共創による取り組みは、「AIが人間の創造性を奪うのではないか」という懸念に対して、「AIを道具として活用することで、クリエイターの表現の幅を広げ、新たな価値を生み出すことができる」という未来の可能性を示したのです。
現代におけるモーツァルトの再解釈 多様な表現
モーツァルトの音楽や生涯は、時代や文化によって様々に解釈され、新たな形で私たちに提示され続けています。これは彼の作品が持つ普遍性と、それを現代の視点から「読み直し」ていくことの面白さによるものでしょう。
ARD(ドイツ公共放送連盟)は、モーツァルトの物語を新鮮かつ現代的に解釈した全4部構成のシリーズドラマ「モーツァルト/モーツァルト」(仮題)を2025年1月に放送予定です。
このドラマでは、これまで兄の陰に隠れがちだった姉マリア・アンナ・モーツァルト、通称「ナンネル」に焦点を当てています。
彼女もまた兄と同じように並外れた音楽の才能を持っていたとされており、その物語を現代的な視点から描くことで、新たなモーツァルト像が提示されることが期待されます。
オペラの世界でも、モーツァルトの名作は現代的な解釈によって新たな魅力を放っています。
新国立劇場ではモーツァルトのオペラ『コジ・ファン・トゥッテ(女はみんなこうしたもの)』を、18世紀のナポリの海辺ではなく、現代のキャンプ場を舞台に上演します。この斬新な演出は「キャンピング・コジ」と呼ばれ、テキストに忠実でありながらも作品に新たな息吹を吹き込み、人気を博しました。
モーツァルトの歌劇「魔笛」も、ブラナーによる新解釈や、南アフリカの現代美術家ウィリアム・ケントリッジによる演出で映像化、上演されています。ケントリッジ版『魔笛』では「動くドローイング」を用いたアニメーションや影絵が多用され、啓蒙主義の危うさや独裁者の側面を現代の視点から描こうとする試みがなされています。衣装や舞台芸術も現代アートの巨匠が手掛けることで、古典作品に新鮮な息吹が吹き込まれています。
映画『アマデウス』(1984年)も、モーツァルトの人物像に大きな影響を与えました。
この映画ではモーツァルトが音楽的才能に優れる一方で、品のない高笑いをしたり、下品な言葉を多用したり、酒好きで浪費家であるといった「破天荒でめちゃくちゃな人物」として描かれました。
この「音楽的才能と突飛で下品な言動のずれ」は、公開当時から史実との違いをめぐる議論を巻き起こしましたが、学術領域だけでなく、オーストリアのミュージシャンであるファルコの楽曲「ロック・ミー・アマデウス」(1985年)や、日本のNHK Eテレのアニメ『クラシカロイド』など、その後のさまざまな文化的領域に影響を与え、今日なおモーツァルトの表象にその面影を残しています。
アニメ『クラシカロイド』ではモーツァルトが「奔放、幼稚、だが天才」と紹介され、遊戯的な言動を繰り返しながらも優れた音楽を発動する天才として登場しています。
このような現代的な再解釈は、演奏の世界でも見られます。
演奏解釈は時代とともに流行と盛衰を繰り返し、常に「読み直し」が行われてきました。
かつては厳格なテンポを守る「原典演奏」が重視された時期もありましたが、現在では原典に忠実であることだけが唯一の正解ではないという考え方も広がっています。
奏者は楽譜に書かれた音符だけでなく、その背景にある歴史や文化、そして自身の感性を加えて作品を「解釈」し、演奏を通じて聴衆と繋がっていくことが求められているのです。
AI作曲ツールが変える音楽制作の現場
AI技術の進歩は、音楽制作の現場にも大きな変化をもたらしています。現在では、プロの音楽制作者から音楽制作に興味を持つ初心者まで、誰もが高品質の音楽を簡単かつ迅速に生成できるAI作曲ツールが数多く登場しています。
代表的なAI作曲ツール
- Suno AI(スノ・エーアイ) は、ユーザーがテキストプロンプトを入力するだけで、歌詞とともに音楽を自動生成します。例えば「Tokyo night」と入力すれば、東京の夜をテーマにした曲が生成されるといった具合です。知識や技術がなくても、ボーカルと非ボーカルの要素が組み合わされた深みのある音楽を作成できるのが特徴です。無料プランでも1日5回の生成が可能で、有料プランでは商用利用も可能です。
- Udio(ユーディオ) は、Suno AIの強力な対抗馬として2024年に登場しました。作曲クオリティの高さが話題で、日本語ボーカルも自然だと評価されています。カスタマイズ機能も充実しており、無料プランでも1日10クレジットの制限がありますが利用できます。オリジナルで生成したコンテンツは商用利用も許可されています。
- AIVA(アイヴァ) は、広告や映画、ゲームなどのサウンドトラック制作に適したAI作曲ツールです。ユーザーは音楽をゼロから作成できるほか、既存の曲のアレンジバリエーションも生成できます。クラシックやポップス、EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)など多様なジャンルに対応しており、無料版でも基本的な機能を利用できます。NVIDIAのドキュメンタリーシリーズでも紹介されており、AIが楽曲のパターン分析をもとに曲の土台を作る一方で、人間が演奏や編曲、盗作チェックなどを行う「AIとの共作」の可能性を探っています。
- SOUNDRAW(サウンドロー) は、AIが無数に生み出すフレーズを組み合わせ、楽曲の尺、構成、楽器、テンポなどを自由にカスタムすることで、オリジナル楽曲を簡単に制作できるサービスです。コンテンツに最適な楽曲を選定する手間と時間を大幅に削減できるため、YouTubeや動画広告、Podcastといったコンテンツ制作に役立っています。
- MuseNet(ミューズネット) は、ChatGPTで知られるOpenAIが開発した深層ニューラルネットワークです。10種類の異なる楽器で4分間の音楽作品を生成でき、クラシックからポップ、カントリーまで、幅広い音楽ジャンルのスタイルを組み合わせることが可能です。モーツァルトやショパンなどのクラシックの巨匠の楽曲と、ビートルズなどの現代アーティストの楽曲を組み合わせて新しい音楽を創ることもできます。
様々なメリット
これらのAI作曲ツールの活用は、音楽制作における様々なメリットをもたらします。
まず、オリジナル楽曲制作のコスト削減です。作曲家への依頼費や編集費を抑え、低コストで高品質なオリジナル楽曲を制作できるようになります。
次に、音楽制作のハードルが下がる点です。音楽制作の知識や経験が少ない人でも、簡単に楽曲を作成できるようになり、クリエイターのモチベーション向上や新たな才能の発掘にも繋がる可能性があります。
さらに、ブランディングや広告での音楽活用が進むことも期待されます。企業イメージに合った楽曲をAIで迅速に生成し、マーケティングやプロモーションに活用することで、印象に残るコンテンツ作りが可能になります。
AIが生成した楽曲は著作権処理が簡単な場合も多く、動画コンテンツや店舗BGMなどにも気軽に利用できる利点があります。
AIを活用したサービスや製品の開発を通じて、新たなビジネスチャンスが創出される可能性も秘めています。AI生成楽曲を用いたゲームアプリや音楽教育ツール、音楽療法など、革新的なサービスが生まれるかもしれません。
今後、問題化しそうな課題
しかし、AI作曲においては重要な課題も存在します。それは著作権の問題です。
現行の法律では、完全にAIのみで作曲された楽曲には著作権が認められません。これはAIが人間よりも素早く大量の楽曲を生成できるため、もしAIに著作権が認められれば、人間の芸術活動を阻害する可能性が高いと考えられているからです。
ただし、「AIを道具として利用しながら人間が作った楽曲」に関しては、人間に著作権が認められます。
Suno AIやUdioなどの自動作曲ツールで作られた曲の著作権は国によって異なる場合もありますが、基本的にはAIが作った曲として著作権は存在しない、という考え方が一般的です。
AIと共に歩む音楽の未来 可能性と課題
AIが音楽の世界にもたらす未来は、単に「AIが人間の仕事を奪う」といった悲観的なものではありません。むしろAIは人間の創造性を拡張し、音楽の可能性を無限に広げる強力なツールとなり得ます。
AIはすでに、作曲のサポート役として大きな存在感を示しています。過去の膨大なデータを学習し、メロディやコード進行を提案することで、作曲家はアイデア出しや初期段階の作業を効率化し、より創造的なアレンジや歌詞付けに集中できるようになります。
これはモーツァルトが「職人」のように速く作曲できたという側面と、現代のAIによる効率化が、ある種の共通点を持っているとも言えるでしょう。
AI技術は、新たな音楽表現のフロンティアを切り開いています。
例えば、ヤマハの歌声合成技術「VOCALOID:AI」は、故人である美空ひばりさんの歌声を再現する挑戦的な取り組みを支援しました。これは、単に過去を再現するだけでなく、新たな解釈や表現の可能性を示唆しています。
AIは今後さらに発展し、オーケストラの作曲を担ったり、ゲームや映画のシナリオを読み込んで場面に応じた楽曲を自動生成したりする機能も、追加されていくと予想されます。
もちろん、著作権問題をはじめとする権利関係の課題は山積しており、今後も議論が続くことでしょう。AIが生成した音楽の品質チェックや倫理的な問題についても、常に注意を払う必要があります。
しかし、これらの課題と向き合い、AIを恐れるのではなく、「AIとうまく共存しながら、より良い音楽をより短い時間で作れるようになっていく」ことが、より豊かな音楽の未来を築く鍵となるのではないでしょうか。
クラシック音楽業界においては、若い世代の関心低下や観客減少といった課題が指摘されています。
AI作曲ツールやAIを活用した現代的な再解釈は、こうした状況を打破し、新しい聴衆を獲得する可能性を秘めています。
他のジャンルの音楽とのコラボレーションや新しい演奏スタイル、そして新しい会場での演奏といった試み。それと並行してAIによるアプローチは、クラシック音楽をより身近なものにし、新たなファン層を広げる一助となるかもしれません。
モーツァルトの時代に革新的な音楽を創造した彼の精神は、現代のテクノロジーと結びつくことで、想像もしなかった「新しいモーツァルト」として私たちの前に現れようとしています。
古典の普遍的な魅力とテクノロジーの無限の可能性が織りなす音楽の未来は、ますます目が離せません。
私たちはこのエキサイティングな変化をオープンな心で受け入れ、共に音楽の新たな地平を探索していくことになるでしょう。
では締めくくりに、正真正銘モーツァルトの手になる清く美しい、心洗われるカノンをご紹介しましょう。『Leck mich im Arsch) K.231』です。
日本語訳ですか?
「俺のケツをなめろ」
です。


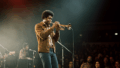
コメント