永遠に愛されるラフマニノフの傑作
セルゲイ・ラフマニノフは1873年にロシアで生まれ、1943年まで生きた偉大な作曲家です。世界中で活躍する、一流のピアニストでもありました。
彼はピアノの名技性とロシア的な特質を併せ持つ、数多くのピアノ曲を生み出しています。
彼が残した4曲のピアノ協奏曲の中でも、第2番はとりわけ人気が高い名曲として知られています。曲の初演から1世紀以上、世界中の人々に愛されてきました。
ラフマニノフの作品は「センチメンタルな旋律美」「雄大なロシア的叙事詩」「華麗なピアニズムの極致」といった言葉に象徴されるように、一般的な聴衆にも感覚的に素直に味わうことができ、分かりやすさと親しみやすさを兼ね備えていると言われます。
この親しみやすさやドラマティックな要素、具体的なイメージを喚起する力が、ラフマニノフの音楽が広く人気を集める理由の一つです。
特にピアノ協奏曲第2番は、多くの映画やテレビ、CM、そしてフィギュアスケートなどでも使用され、その心に訴えかける強さが多くの人々の記憶に残ります。「恋愛の曲」として、甘く切ない旋律が愛の物語を彩ってきました。
スランプからの復活 ラフマニノフの苦悩と希望
このピアノ協奏曲第2番が生まれた背景には、ラフマニノフの深い苦悩と、そこからの劇的な復活の物語があります。
作曲に取り掛かったのはピアニストとしてロンドンで成功を収めた際に、現地の団体から作品を依頼されたことがきっかけと言われています。しかし、当時の彼は作曲面で深刻なスランプに陥り、なかなか筆が進まない状態でした。
このスランプの背景には、1897年に作曲した交響曲第1番の初演が惨憺たる失敗に終わったことが大きく影響しています。この作品を先輩作曲家や評論家から酷評され、ラフマニノフはひどく打ちのめされ神経を衰弱し、自信喪失の状態に陥ってしまったのです。その結果、彼は約3年もの間、作曲することができませんでした。
交響曲第1番の失敗の原因については、初演で指揮したグラズノフが酒に酔ってまともに指揮ができなかったという有名な逸話があります。
最近の研究ではこれは誇張された作り話であり、実際はペテルブルク楽壇とモスクワ楽壇の対立による派閥争いが原因だったようです。
ラフマニノフ自身はグラズノフ(両楽壇の折衷派)の指揮について、「まるで何も感じていない、何も理解していないかのよう」だったと、批判的なコメントを残しています。
作曲ができない苦しい時期でも、ラフマニノフが音楽から遠ざかることはありませんでした。彼は指揮者として精力的に活動し、瞬く間に高い評価を獲得します。
文豪トルストイとの面会も試みましたが、トルストイの才能を目の当たりにしてかえって自信をなくしてしまったエピソードも残されています。
そんな彼を救ったのが、精神科医ダーリ博士でした。博士の暗示療法によってラフマニノフは作曲への自信を取り戻し、1900年からピアノ協奏曲第2番の作曲を再開します。
まず、第2楽章と第3楽章を完成させ、1900年12月にこれら2つの楽章が初演されると聴衆は熱狂し、大成功を収めました。そして1901年10月27日に全曲が初演され、再び大成功を収めます。この作品は、彼を治療したダーリ博士に献呈されています。
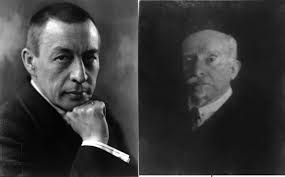
ピアノ協奏曲第2番の成功により、ラフマニノフは作曲家としての名声を不動のものとしました。ただしダーリ博士の貢献について、近年では誇張や作り話が混じっているというのが定説です。
楽曲の魅力と特徴 聴きどころを紐解く
ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番ハ短調 作品18」は、1898年(?)から1901年にかけて作曲されました。演奏時間は約35分です。編成はフルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、テューバ1、ティンパニ、大太鼓、シンバル、弦5部、独奏ピアノという大規模な編成で、伝統的な3楽章構成をとっています。
第1楽章 (Moderato)
ソナタ形式で書かれています。
冒頭はロシア正教会の鐘の響きを思わせるピアノ独奏の重い和音で、厳粛に開始されます。この鐘の音は創作意欲に大きな影響を与えた、ラフマニノフのトレードマークとも言えるでしょう。
次にピアノの情熱的な分散和音に乗って、弦楽器とクラリネットがロシアの広大な大地を思わせるような深く朗々とした第1主題を奏でます。この主題は「ドーレ、ドーレ」と繰り返す2度上行の動きが特徴的です。
やがて甘く切ない第2主題がピアノを中心に歌われ、オーケストラが絶妙に絡み合います。この主題からは、何か深い憧れのような感情が聴き取れます。
第1楽章のピアノパートは非常に高度な技巧が要求され、特に冒頭の和音連打ではピアニストが一度に10度の間隔に手を広げなければならない箇所もあります。ラフマニノフ自身も、2つ目の和音からは時間差で和音を演奏していました。
展開部ではピアノとオーケストラとの対話が進み、ドラマティックに盛り上がりを見せます。
再現部で第1主題がまるで行進曲のように力強く変化し、曲の印象が大きく変わるのも特徴です。
第2楽章 (Adagio sostenuto)
甘美な情感に満ちた緩徐楽章です。
弦楽器を中心とした悲しげな演奏の後、静かなピアノ独奏が響きます。そこにフルートの伸びやかで静かな、そして美しい音色が加わり、ピアノとフルートで主題が演奏されます。
フルートと交代したクラリネットも、ピアノとともに主題を演奏し、全体にとてもゆったりとした中に虚しさや悲しみを感じさせます。
曲はゆったりとした調子のまま進みますが、やがてピアノの音色が熱を帯び始め、気持ちの高まりを感じさせる音色になります。
第3楽章 (Allegro scherzando)
力感に満ちた主要主題と、息長く歌われる副主題が劇的な展開を生み出すフィナーレです。
第1楽章・第2楽章とは異なり、明るい雰囲気で力強く、スピーディーに始まります。情熱的なステップでもしているかのような第1主題が登場し、聴き手を惹きつけます。
その後、徐々にスピードをゆっくりにしてから、「ドレミファソラシド」というシンプルな音階を並べた、印象的な第2主題が登場します。この第2主題は、音階を上げ下げするだけなのに非常にドラマティックに聞こえ、この楽章の圧倒的主役と言えます。
一旦穏やかな演奏になった後、再び激しく情熱的な演奏が展開されます。そして3回目に登場する第2主題は、ピアノとオーケストラ全体での「巨人的」な演奏となり、その迫力は圧巻です。それまでの苦難の道のりがついに終わりを迎え、新たな始まりに向かって羽ばたいていくような、深い感動をもたらすのです。
映画やフィギュアスケートを彩る名曲
ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番が世界的に広く知られるようになったのは、ラフマニノフの没後、特に1945年に公開されたデヴィッド・リーン監督によるイギリス映画『逢びき』(Brief Encounter)が大きなきっかけです。
曲の切なく甘美な旋律が、中年の淡い不倫の恋というメロドラマのムードをいやが上にも高め、多くの映画ファンを魅了しました。
この作品の使用により、「ラフマニノフの2番」は「恋愛の曲」というイメージが定着しました。
他にも、マリリン・モンロー主演の『七年目の浮気』(The Seven Year Itch、1955年)や、ジョーン・フォンテイン主演の『旅愁』(Intermezzo、1950年)など、印象的にこの曲が使われています。
『七年目の浮気』では主人公が音楽を選ぶ場面で、ドビュッシーやラヴェル、ストラヴィンスキーといった他の作曲家の名前を挙げた後に、「やっぱりラフマニノフだ」とこの曲を選ぶシーンがありました。
アニメでは『のだめカンタービレ』でも使用され、クラシックファン以外にも広く知られるきっかけとなりました。
フィギュアスケートの世界では、浅田真央選手、伊藤みどり選手、高橋大輔選手、村主章枝選手など、数多くの著名なスケーターがこの曲を演技に使用し、観客に深い感動を与えてきました。特に浅田真央選手がソチオリンピックのフリープログラムで使用した演技は、多くの人々の記憶に強く残っています。
ラフマニノフの音楽はその親しみやすさ、ドラマティックな展開、そして具体的なイメージを喚起する力が強いため、これらの多様なメディアで広く人気を集めてます。
特に映画において、監督が主人公の心の動きに曲の同じフレーズやモチーフを同期させることで、より分かりやすく観客に心情を伝えようと意図していた可能性があります。例えば第1楽章のホルンのメロディー部分は、恋愛の切なさや好きな人への思いにふけるシーンに適しており、聴き手に夢の中にいるような不思議な感覚を与えます。
名盤・異色盤・隠れた名盤
ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番について、名盤、異色盤、珍盤をそれぞれ2枚ずつご紹介します。
名盤(広く愛され、高く評価されている録音)
スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ)、スタニスラフ・ヴィスロツキ(指揮)、ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団(1959年録音)
「ラフマニノフの王道」「伝説のラフマニノフ」と称されることもある盤です。
リヒテルは出だしの深さからして他とは一線を画しており、スケールの大きい重厚感がありながらも流れるような抒情性に不足がなく、音色の美しさも特筆されます。
第1楽章の驚くほど遅いテンポでの沈み込むような表現や、第2楽章の暗いロマンの香りなど、聴きどころ満点です。
リヒテルの演奏の中でも、「トップを争うほど出来が良い」とされる一枚になります。
セルゲイ・ラフマニノフ(ピアノ、自作自演)、レオポルド・ストコフスキー(指揮)、フィラデルフィア管弦楽団(1929年録音)
作曲者自身による演奏であり、「歴史的名盤」として非常に高いクオリティを持っています。録音は古いもののラフマニノフ自身のピアノの腕前は非常に高く、表現も洗練されており、現在聴いても十分に楽しめるはずです。
情緒に流されることなく、高い品格を持ってしっかりと弾かれており、テンポや弾き方などから多くの発見がある貴重な録音です。
今日のスタンダードな作品解釈と大きな違いはなく、演奏の大きな手がかりとなる資料としても貴重です。
異色盤(独特の解釈やスタイルで注目される録音)
アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)、ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1972年録音)
ワイセンベルクのピアノは「情緒を極力排した堅く引き締まった音色」と評され、音楽が期待する情緒に左右されない「機械のような進行」が特徴的です。
カラヤンの指揮と相まって「コズミックファンタジー」や「音楽の新世紀を切り開いた」とまで形容されるほど、非常に独特な解釈が施されています。
クールな抒情とでもいうのでしょうか。二律背反を成し遂げたコンセプトが明確で、徹底されている演奏です。
エレーヌ・グリモー(ピアノ)、ウラジミール・アシュケナージ(指揮)、フィルハーモニア管弦楽団(2000年録音)
グリモーの演奏は速めでスタイリッシュであり、リヒテルやアシュケナージの演奏と比較して、モダンで色彩的な演奏です。
伝統的な「ロシア的重厚さ」はあまり感じられないものの、物足りなさはなく、非常に新鮮な印象を与えます。
アシュケナージの伴奏もロマンティックで、グリモーの多彩なニュアンスと歌い方のセンスが際立つ演奏です。
隠れた名盤
ヴィクトール・エレスコ(ピアノ)、プロヴァトロフ(指揮)、ソヴィエト国立交響楽団(1984年録音)
エレスコはロン・ティボー・コンクールで優勝しているものの、日本では無名に等しく、一般的な知名度は総じて低いようです。
この録音はロシア勢の演奏であり、「フォルテ部分の荒々しさ」が魅力です。
「ハリウッド風の甘さ」はなく、ラフマニノフがロシア時代に書いた曲であることを改めて認識させる演奏になります。
リヒテルと比べるとスケールの大きさで劣るものの、静かに沈滞する部分ではロシアの憂鬱をしっかり表現している点が特徴です。
アレクセイ・スルタノフ(ピアノ)、マキシム・ショスタコーヴィチ(指揮)、ロンドン交響楽団
この録音はスルタノフが19歳だった頃の演奏です。
1989年にヴァン・クライバーン・コンクールで優勝し、95年にはショパン・コンクールで2位になるなど、若くして才能を発揮しながら、2005年に35歳で早世したピアニストの貴重な記録です。
彼の演奏は若々しい詩情とデリカシーに満ちており、ショスタコーヴィチの息子であるマクシム・ショスタコーヴィチの指揮も貴重で、感動的な大きな流れを作っています。
一般的な名盤として挙げられるわけではないものの、多くの人に聴いていただきたい一枚になります。
作曲技法の秘密 旋律と和声、リズムの深遠
ラフマニノフの音楽の根幹をなす要素は、何よりもその「旋律」にあります。彼自身が「旋律が音楽であり、音楽の基礎である」と語るように、旋律重視の音楽観が彼の作品全体を貫いています。
その旋律は「息の長い」ことで知られ、ロシア聖歌の抑揚に基づいている可能性も指摘されています。
順次進行を主体としつつも、シンコペーション、弱拍出、リズム分割、反復進行といった多様な要素を組み合わせることで、独特の抑揚と色彩感を生み出しています。
「ラフマニノフ・リズム」と呼ばれる彼独自のリズムパターンは作品に特有の躍動感を与え、その音楽を特徴づける重要な役割を担っています。
和声面では明確な調性感を持つ伝統的な機能和声に基づきつつも、半音階的和声や全音音階も部分的に用いることで、複雑な和声構造を作り上げています。
彼の作品は短調が多く、長調の主題であっても短調への傾斜を伴う和声付けが施され、独特の憂鬱な情緒を醸し出しています。
IV度の変化和音やナポリの六の和音といった、同主短調からの借用和音の使用が、頻繁に見られます。
曲の冒頭やクライマックス部分などで低音部の根音を持続させる「オルゲルプンクト効果」を好んで用いました。これはしばしばロシア正教会の鐘の音にたとえられ、壮大な響きを生み出す効果があります。
ラフマニノフの作曲姿勢で特筆すべきは、「変容の作曲家」としての側面です。作品の主題や動機素材を、様々な形で「変容」させながら繰り返し用いることを特徴としています。
動機的処理や循環手法を巧みに用い、全曲を有機的に統一する彼の構成観は独特です。
「ラフマニノフ予告」という、重要動機の反復を最小限に抑えつつ聴衆の潜在意識に印象を残す特殊な手法や、「ラフマニノフ変化」と呼ばれる、主題のごく一部分の音のみを明確な根拠なく変化させる独特な技法も用いています。これらの「かくし味」によって彼の音楽は、さらに複雑で深遠なものとなっているのです。
特定の音型や楽想を繰り返し使用する「反復癖」も指摘されますが、それを単調にせず、常に個性豊かな音響と表現効果を生み出すのが、ラフマニノフの巧妙な作曲技法と言えます。
管弦楽法においても、ラフマニノフは緻密な音響設計と綿密な計算に基づいた技法を確立していました。弦楽器の細分割や、音色変化を求める修飾法など、様々な工夫が見られます。
彼のピアノ作品には、純粋なピアニスティックな要素だけでなく、複雑な音群の融合体や多旋律の線的な相互交錯性といった管弦楽的性格が色濃く現れています。
これは彼が創作初期からピアノに限定せず、交響作品にも積極的に取り組んでいたことに由来するのでしょう。
ラフマニノフの音楽は革新性や創造性の面で音楽史に大きな貢献をしたわけではなく、むしろ保守的な創作態度と見られることもあります。
メンデルスゾーン、サン=サーンス、ブラームスなど、同系列の作曲家に分類されることもあり、チャイコフスキー、グラズノフ、スクリャービン、シューマン、アレンスキーなど、同時代の多くのロシア作曲家や後期ロマン派の作曲家との旋律的、和声的類似点も指摘されています。
ラフマニノフはこれらの影響を独自に消化し、個性的な音楽様式を確立した「変容の作曲家」として、その真価を発揮したのです。
変容の作曲家
ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は、今日においてもその音楽的価値は普遍的であり、世界中の多くの聴衆と演奏家に愛され続けています。
この作品は、作曲家自身のスランプからの復活というドラマティックな物語を背景に持ち、聴き手を惹きつける壮大な楽曲構造、そして映画やフィギュアスケートといった多岐にわたるメディアでの活用を通じて、その魅力を広めてきました。
数々の名演奏の存在も、不朽の地位を確固たるものにすることに貢献しています。
ラフマニノフの音楽をより深く理解するには、その楽譜の内面に秘められた「隠し味」や、彼が用いた緻密な作曲技法を探求することが重要です。
彼は先人からの影響を受けつつも、それらを独自に昇華し、個性的な音の世界を再構築していった「変容の作曲家」と言えるでしょう。
ラフマニノフの作品はこれからもさらに深く研究され、多くの人々に愛され続けることでしょう。

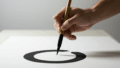
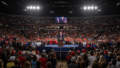
コメント