石川さゆりさんの「津軽海峡・冬景色」は1977年に発売されて以来、多くの人々に愛され続けている特別な歌です。世代や時代を超えて日本人の心に深く刻まれています。なぜこれほどまでに多くの人を魅了し続けるのでしょうか。その普遍的な魅力と秘密を一緒に見ていきましょう。
イントロと歌い出しに隠された仕掛け
この歌の大きな特徴は、私たちを瞬時に物語の世界へと引き込む力です。作詞家の阿久悠さんと作曲家の三木たかしさんは、聴く人を「津軽海峡」へと連れて行くための仕掛けを用意しました。
まず、曲の始まりにある「ダ・ダ・ダ・ダーン」というインパクトのあるイントロです。三木たかしさんは、冬の津軽海峡の厳しさや荒々しさ、そしてもの悲しさを表現するために、この部分を歌のメロディーよりも先に作ったと言われています。このたった一フレーズで、聴く人は荒波が打ち寄せる冬の岸壁に一人立っているような気分になります。
歌詞の冒頭も非常に印象的です。「上野発の夜行列車降りた時から 青森駅は雪の中」という表現は、小説「雪国」のように劇的な場面転換を鮮やかに描きます。動詞が少ないにもかかわらず、「夜行列車」や「雪の中」といった「動き」を感じさせる言葉が使われており、聴き手はすぐにその情景に「ワープ」してしまうのです。
石川さゆりさんの唯一無二の歌唱法
石川さゆりさんの歌唱は、「津軽海峡・冬景色」が時代や世代を超えて愛される名曲となった重要な要素であり、その心揺さぶる歌声には様々な「仕掛け」と背景があります。
声質と響かせ方
彼女の声は強く鋭いながらも、どこか切なく透き通っており、まるで三味線の音色のようです。
歌声は体の深い位置から発せられ、お腹の前や上部で強く前に押し出しつつ、額のあたりで響かせるのが特徴的です。これは演歌の歌唱法に共通するポイントとされています。
ポップスとは異なり、口を縦に大きく開けず、鼻腔を閉じた鋭い歌声を出す歌い方になります。
「コブシ」と感情表現
サビに入る直前の「あぁあぁぁ」という歌声は、演歌独特の「コブシ」と呼ばれる歌唱法です。地声から裏声へと切り替わる際の、まるで6度も跳躍するような表現が、聴く人に強いインパクトを与え、主人公の感情の揺らぎを見事に表現します。このコブシは石川さゆりさん唯一無二のものと言っていいでしょう。
感情を直接的な言葉で表現する代わりに、歌声の揺れで心の揺らぎを表現しているのです。
彼女は「寂しいから寂しいと歌うのはどうなんだろう」と自らに問いかけ、感情を直接伝えるよりも、聴き手の心に情景や想いを重ねてもらうべきと考えます。この「歌の美学」に、第一線で活躍する歌い手の深い洞察が垣間見えます。
言葉の強調とテンポの意識
フレーズの最後に余韻を持たせ、オンテンポではなくかなり後ろに言葉を置くことで「タメ」を作り、歌詞の印象を強くするのがポイントです。
子音をしっかり強く発音して、言葉をより強調します。
歌詞のない間奏部分で感情を込めやすく、石川さゆりさんの「ああ」は抜群の表現力で曲にインパクトを与えています。
表現力と物語性
「津軽海峡・冬景色」は阿久悠氏が作り上げた歌詞の世界観を三木たかし氏が広げ、それを歌唱力・表現力抜群の石川さゆりさんが歌い上げた結果、長年愛される名曲となりました。
彼女は優れた語り手であり、歌詞の意味を知らなくても歌声だけで物語に入り込めるような魅力を持っています。
歌い出しの「上野発の夜行列車降りた時から」では、動詞が「降りた」だけなのに、「夜行列車」や「雪の中」といった「動き」を感じさせる言葉で、聴き手をすぐに情景の中に「ワープ」させる力があります。
「凍えそうな鴎見つめ 泣いていました」といった情景描写を通して、主人公の深い心情を間接的に表現し、聴き手に共感を呼び起こします。
「私もひとり 連絡船に乗り」という歌詞の「も」は、主人公が周りの無口な人々と同じように一人であること、あるいは大勢の中の一人に過ぎないという孤独感を伝える、奥ゆかしい表現です。
歌唱の進化と挑戦
石川さゆりさんはこの曲を、長年歌い続けることで表現力を深めていきます。
当初は19歳(1977年当時)という若さでありながら見事に歌い上げ、本格的な演歌歌手に変貌を遂げるきっかけとしました。
彼女は常に新しい刺激を追求する現役のヴォーカリスト兼エンターテイナーであり、さまざまなジャンルのミュージシャンとのコラボレーションも積極的に行い、歌唱をアップデートし続けています。そうした努力の結果、「津軽海峡・冬景色」や「天城越え」の円熟度も増しているのです。
歌詞に込められた深い情景と感情
「津軽海峡・冬景色」は、その情景描写の豊かさと感情表現の奥深さによって、多くの聴衆の心を掴んで離さない名作です。
物語の舞台と背景
この歌は東京の上野駅から夜行列車に乗り、青森駅で降り、津軽海峡を越えて北海道へ向かう人々の様子を描いた叙事詩です。主人公は傷心を抱え、北海道へ帰る旅路にあります。
元々は、少女が大人の女性に成長していく1年間を12曲で描いたコンセプトアルバム『365日恋もよう』の最後、12月の曲として制作されました。
発売当時(1977年)は円高不況の時代であり、この歌は斜陽に向かっていた青函連絡船と津軽の厳しい冬景色、不況にあえぐ人々を歌い上げる哀歌として受け入れられました。青函連絡船が1988年に廃止されたことで、昭和という時代の郷愁を誘う曲としての価値も加わります。
石川さゆりさんは、阿久悠さんの詞には「時代性」とともに「行間」がたくさんあり、歌い手も聴き手もそれぞれの中に景色や想いを重ねていけると語っています。
歌詞の始まり方と情景への「ワープ」
歌い出しの「上野発の夜行列車降りた時から 青森駅は雪の中」というフレーズ、聴く人を一瞬でその情景の中に引き込む「ワープ力」が発揮されます。
動詞は「降りた」だけですが、「上野発」「夜行列車」「雪の中」といった「動き」のある言葉が使われ、聴き手を瞬時に物語の世界へと誘うのです。川端康成の『雪国』の「トンネル」に代わり、「夜行列車」が使われているためでしょうか。
感情の「間接表現」と共感
「津軽海峡・冬景色」の歌詞は、主人公の感情を「悲しい」「苦しい」「辛い」といった直接的な言葉で表現していません。代わりに「凍えそうな鴎見つめ泣いていました」といった情景描写を通して、主人公の深い心情(心の寒さ)を間接的に表現しています。
この間接表現によって聴き手は自身の経験や感情を重ね合わせやすくなり、「こんな感じ、わかる」との共感を呼び起こします。このように情景描写のみで感情を伝える手法は、俳句に似ているという指摘もあります。
「無口な人々」と「も」の意味
「北へ帰る人の群れは誰も無口で」歌詞は周りの人々が皆静かであることを示していますが、実際の夜行列車内は長旅で賑やかだったという話もあり、歌のイメージとは異なるようです。
しかしこの「無口」な描写は、主人公の傷心の帰郷の雰囲気に合致します。周囲が賑やかであるほど孤独が募る、逆説的な解釈も成り立つわけです。北国の寒さが口を開くことをためらわせる、あるいは北の人々の県民性を表しているという見方もあります。
「私もひとり連絡船に乗り」というフレーズの「も」という助詞は非常に重要です。
もし「私はひとり」であれば単なる報告になるのに対し、「私もひとり」とすることで、周りの人々も自分と同じように一人であること、あるいは自身が大勢の無口な人々の中の一人に過ぎないという孤独感を、奥ゆかしく表現しています。
これこそは日本語の持つ繊細さの、良き例となるでしょう。
「竜飛岬」の象徴性
「ごらんあれが竜飛岬 北のはずれと」の「竜飛岬」は本州の最北端に位置する場所です。歌碑も建立されています。
「息でくもる窓のガラス ふいてみたけど かすかにかすみ 見えるだけ」という描写は、窓を拭いても遠くの景色が霞んで見えるだけで、主人公自身の未来が見えない心の状況を表現していると解釈できます。
「さよならあなた 私は帰ります」に込められた意味
このフレーズは、それまでの耐え忍ぶ演歌の女性像とは異なり、主人公が自らの意思で行動し、自立した女性の強さとしなやかさを提示しています。
この「帰る」という言葉は、心の整理がある程度ついたことを示唆し、聴き手に安堵感を与えます。
石川さゆりさん自身も、歌は感情を直接伝えるだけでなく、聴き手の心に情景や想いを重ねてもらうものだと考えているそうです。
このフレーズには彼女の「歌の美学」が込められています。
歌詞の韻律と作曲との連携
歌詞は言葉の響きが美しく、不自然さを感じさせません。Aメロやサビ前では、3音や4音で文節が区切られるなど規則的なリズム感があり、これが歌いやすさや心地よさにつながっています。
阿久悠氏は石川さゆりさんの濁りのない声に合うよう、七五調よりも「三、三、三と転がっていくような詞」を意識したと述べており、これがカンツォーネのような軽快さを生み出しています。
わずか5分で作られた曲
「津軽海峡・冬景色」の作曲は、三木たかしさんが手掛けています。彼の作曲は、時代や世代を超えて愛される名曲となった重要な要素の一つです。
作曲のプロセスと速さ
この曲はタイトルが先に決められており、そのタイトルに三木たかしさんが曲をつけ、その後に阿久悠さんが詞を作ったという経緯があります。阿久悠さんからは「歌の最後は『津軽海峡冬景色』というフレーズで終わってほしい」という要望があったそうです。
三木たかしさんは若い頃、青函連絡船に乗って札幌へ行った帰りに雪が降ってきた光景を思い浮かべ、その時の想いが湧き出て約5分でこの曲を作曲したと語っています。三木氏は短時間で一気に作り上げた曲の方が、ヒットする傾向にあると述懐しています。
曲のメロディーよりも先に、「ダ・ダ・ダ・ダーン」という激しいイントロが最初に出来上がりました。このイントロは、冬の津軽海峡の厳しい寒さ、海の荒々しさ、凍るような感覚、そして物悲しさを表現しており、ベートーベンの「運命」のようなインパクトがあります。このイントロがその後のメロディーのベースとなり、曲の核となっていきます。石川さゆりさんは初めてこのイントロを聴いた時、「何だこの曲は」と衝撃を受けたそうです。
音楽的な特徴
楽曲のキーは、Aマイナー(am)です。
「津軽海峡」の「い」の音は一番高い「レ」の音で、歌の要となっています。
この曲には「三連符」のリズムが使われており、これが名曲としての軽快さや心地よさにつながっています。Aメロやサビ前では3音や4音で文節が区切られるなど、規則的なリズム感があります。
サビの後半のメロディーとリズムは、演歌というよりロックのようであると評する人もいます。
「私もひとり連絡船に乗り」の部分では、バス(低音)がFからHへ増4度上がる「ドッペル・ドミナント」という和声が用いられており、劇的で情熱的、ロマンティックな効果を生み出しています。これはベートーベンやモーツァルトの作品にも見られる手法で、「クラシックのゆえんをおさえている」三木たかしの和声は、「隠し味に満ちていて、何度聴いても飽きない」と評されます。
歌い出しの「上野発の夜行列車」のメロディーは、シューベルトの「セレナーデ」の「秘めやかに(闇をぬう)」「静けさは~果てもなし」のフレーズと同じ音素材とリズムで6度跳躍が現れ、この跳躍が聴く人に強いインパクトを与えています。
作曲家の哲学と展望
三木たかしさんは、「美しさやもの哀しさが感じられるようなメロディーの枠組みはもう出尽くしてしまった」と考えており、新しい感性の音を見つけられない限り、歌謡曲は行き詰まるのではないかと述べていました。
彼は、若者が「カッコよさやファッション」でアメリカの音楽を聴く現状を「寂しい」と感じ、「ナショナリティがない」と指摘しています。しかし、津軽三味線を弾く若者が出てくるなど新しい動きもあることから、今後の音楽界に期待も寄せていました。
三木たかしさんはテレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」や「アンパンマンのマーチ」、「夜桜お七」など、数々のヒット曲を生み出しています。
彼は、第19回日本レコード大賞で「思秋期」「津軽海峡冬景色」などの作曲により、中山晋平賞(作曲賞)を受賞しています。
時代を超える「年の瀬の風物詩」
「津軽海峡・冬景色」は、毎年年末に放送される「NHK紅白歌合戦」の「風物詩」として定着しています。2007年以降は、もう一つの代表曲「天城越え」と交互に歌われるようになり、この歌が流れると「ああ、今年ももうすぐ終わるなあ」と感じる人も多いことでしょう。
歌の中に登場する「青函連絡船」は1988年に廃止されましたが、それがかえって昭和という時代の懐かしさを感じさせ、歌にさらなる深みを与えています。
この曲の人気は日本国内にとどまりません。海外のリスナーからも、「歌詞は分からないけれど、歌を聴いているだけで涙が出てくる」「彼女の声は私の魂に直接語りかけてくる」といった感動の声が寄せられています。アメリカのギタリスト、マーティ・フリードマンさんは、この歌をきっかけに日本語を学び始めたほどです。
「津軽海峡・冬景色」はその力強い導入、情感豊かな歌声、そして深い情景描写で、私たちを遠い北国の旅へと誘い、心に残る感動を与え続けているのです。


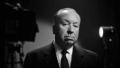
コメント