西洋音楽の伝統から生まれた未知の響き
「現代音楽」と聞いて、どんな印象をお持ちでしょうか?「難解」「とっつきにくい」「音がバラバラ」「メロディがなく捉えどころがない」といった印象をお持ちの方が、大半かもしれません。
確かに、バッハやモーツァルト、ベートーヴェンといった伝統的なクラシック音楽とは大きく異なる響きを持つ曲が多いことは事実です。しかし、現代音楽は決して特別な音楽ではありません。それは数百年にわたって受け継がれてきた西洋クラシック音楽の歴史の中から生まれ、発展してきた「新しい時代の音楽」なのです。
現代音楽はどんな音楽で、なぜ生まれたのか、そしてどうすれば楽しめるのでしょうか。
現代音楽といっても、ヒットチャートに並ぶような「現代の」音楽とは異なるジャンルです。
一般的には1900年代以降、従来のクラシック音楽のスタイルから一歩踏み出した先鋭的な音楽のことを指します。
その最大の特徴は、長調や短調といった「調性」のルールから離れ「無調」の音楽が生まれたこと、そして不協和音が多用されることです。
なぜ、これまでの心地よい響きを持つ音楽から、大きく異なるスタイルの音楽が生まれたのでしょうか。そのような音楽を、誰が必要としたのでしょうか。
背景には19世紀のロマン派音楽が豊かな感情表現を追求する中で、調性という枠組みの限界に近づいていったことがあります。
作曲家たちは新しい表現方法や響きを求め、従来のルールにとらわれない自由な音楽の創造を目指しました。
第一次世界大戦やロシア革命といった20世紀初頭の社会的な激動が、19世紀的な理想や夢の世界観を打ち砕き、音楽のあり方に変化をもたらしたという見方もあります。
音楽だけじゃない 現代アートとの深い関係
現代音楽は単に、音楽史上の新しい時代区分であるだけでなく、「コンテンポラリー アート(現代芸術)」という大きな芸術の流れと深く結びついています。
聴き手に広く受け入れられることよりも、純粋に芸術的な探求やコンセプトの追求を重視する姿勢を持っているのです。
これは絵画や彫刻といった他の現代アートが、分かりやすさよりも芸術性や知性を優先する傾向と共通しています。
フランスでは現代音楽を含む芸術音楽を、「musique savante(教養のある人のための音楽)」と表現することもあるくらいです。
歴史的にも現代音楽は、同時代の他の芸術分野から様々な影響を受けてきました。
音楽以外の造形美術や現代アート、映画制作の技術から着想を得て作曲した人もいます。
例えばジョン・ケージの有名な作品「4分33秒」(無音の楽曲とされる)は、美術家ロバート・ラウシェンバーグの何も描かれていない白いキャンバスの絵画や、マルセル・デュシャンの既製品の便器を作品とした「泉」といった、現代美術作品に影響を受けて生まれたと言われます。
ダダイスム、フルクサス、ミニマリズムといった美術史上の重要な運動とも関連があります。
例えば反復を特徴とするミニマル ミュージックは、同時期に美術の世界で起こったミニマル・アートと関連付けられます。
文学や詩からインスピレーションを得た作品も多く、日本の作曲家である武満徹は詩人・谷川俊太郎の詩に基づいた作品を書いています。
演劇やバレエの音楽も現代音楽の重要な一部であり、ストラヴィンスキーのバレエ音楽「春の祭典」は、現代音楽の幕開けを告げる作品の一つとされています。
現代音楽を特徴づける多様なアプローチ
現代音楽が「難解」と感じられる一因に、その作曲技法やアプローチの多様性があります。従来の音楽のような調性やメロディの規則性に依らない、様々な新しい手法が開発されました。
無調と十二音技法
後期ロマン派音楽の拡張された調性から無調への移行は、ワーグナーの「トリスタン和音」に始まり、シェーンベルクによって明確な形となりました。
シェーンベルクが開発した「十二音技法」は1オクターブ内の12の音を全て平等に使い、特定の音を中心としない無調の音楽を組織的に作り出す方法です。
この技法は音の高さだけでなく、音の長さ、強弱、音色といった要素にも適用される「セリエル音楽」や「トータル セリエリズム」へと発展しました。
偶然性の音楽
アメリカの作曲家ジョン・ケージは、西洋音楽における作曲家による音の厳密なコントロールという考え方に見直しを求め、「偶然性の音楽」を創始しました。
東洋思想である易経や禅に影響を受け、サイコロやコイン投げといった偶然の要素を作曲や演奏に取り入れました。これにより音を、作曲家の意図から解放しようとしました。
電子音楽とミュジーク コンクレート
第二次世界大戦後、科学技術の発展は音楽にも大きな影響を与えました。電子的に音を作り出す「電子音楽」や、自然界の音や生活音などを録音・加工して音楽を構成する「ミュジーク・コンクレート」が誕生します。
フランスのピエール・シェフェールはミュジーク・コンクレートの基礎を築き、これによりノイズなども音楽の要素として扱われるようになりました。
スペクトル楽派
フランスを中心に発展したスペクトル楽派は、科学的な手法である音のスペクトル解析を用いて音楽を構成します。これは科学技術と音楽の関連を示す例であり、フランスにはIRCAM(フランス国立音響音楽研究所)のような研究機関も設立されています。
ミニマル ミュージック
1960年代にアメリカで生まれたミニマル ミュージックは、短い音の断片を執拗に反復することで音楽を作ります。繰り返しの過程でパターンが少しずつ変化していくのが特徴です。
現代音楽の中では比較的聴きやすいスタイルとされ、調性的な響きを持つ曲も多くあります。テリー・ライリーやスティーブ・ライヒらが代表的な作曲家です。
「難解」ってホント?聴きやすい名曲おすすめ3選とその魅力
なぜ現代音楽は「難解」に感じられるのか。おすすめの作品に入る前に、多くの人が現代音楽を「難しい」と感じる背景について、少しだけご紹介します。
調性からの脱却と不協和音
ロマン派までの音楽にあった「調性」(長調や短調といった、中心となる音や心地よい響きのルール)から離れ、「無調」や多くの不協和音を使う作品が増えました。これは私たちが普段聴く多くの音楽(J-POPなども含む)が調性に基づいているため、耳慣れない響きに戸惑いを感じやすいためです。
「垂直方向の響き」
従来の音楽がメロディやハーモニーの流れ(「水平方向」)を重視したのに対し、現代音楽は瞬間的な音の重なりや質感(「垂直方向」)に焦点を当てることがあります。突然大きな音が鳴ったり、予期せぬ音が現れたりすることで、聴き手を戸惑わせるのです。
コンセプトや理論の重視
聴いていて心地よいか、だけでなく、芸術的なコンセプトや論理的な構成(例えば十二音技法やセリエリズムなど)を追求することが少なくありません。
音楽以外の分野(現代アートや哲学など)との関連も深く、その背景を知ることでより深く味わえる側面もあります。
しかし、これらの特徴を持つ作品ばかりではなく、多様なスタイルが存在する点が現代音楽の面白さでもあります。
初心者におすすめの現代音楽3選
それでは、入門編として特におすすめの3作品をご紹介します。
クロード・ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲
- 作曲家: クロード・ドビュッシー(1862-1918) – フランスの作曲家。
- なぜおすすめ? この曲はしばしば、「現代音楽の始まり」「新しい時代の到来を告げた」作品とされています。
それまでの機能和声(調性のルール)にとらわれず、色彩や印象を音楽で表現しようとした点が革新的でした。
しかし、その響きは「新しいハーモニー感に裏打ちされた美しいサウンド」に満ちており、「メチャクチャ美しい」と感じる人も多い作品です。一般的には「クラシック音楽」として普通に聴かれており、「現代音楽」という意識を持たずに鑑賞されています。
新しい時代の幕開けでありながら耳に心地よい美しさを持つため、伝統的なクラシックから現代音楽へのスムーズな入り口として最適です。
スティーヴ・ライヒ:ミニマル・ミュージック(「18人の音楽家のための音楽」)
- 作曲家: スティーヴ・ライヒ(1936-) – アメリカの作曲家。ミニマル・ミュージックの重要な創始者の一人です。
- なぜおすすめ? ミニマル・ミュージックは他の現代音楽のスタイルと比較して、「非常に聴きやすく」「親しみやすい」と評されます。短い音のパターンを繰り返し、それを少しずつ変化させていく手法が特徴です。
執拗な反復の中に生まれる微妙な変化や、音の重なりが生み出す響きに耳を傾ける面白さがあります。瞑想的な効果を感じるという人もいます。
シェーンベルクら難解とされる無調音楽とは異なるアプローチで、リズムや反復に関心を持つ方には特に分かりやすい入門となるでしょう。
「18人の音楽家のための音楽」は、その代表作として挙げられます。
吉松隆:ピアノ協奏曲「メモ・フローラ」
- 作曲家: 吉松隆(1953-) – 日本の作曲家。ポップスと現代音楽の両方を愛するユニークな経歴を持ちます。
- なぜおすすめ? 吉松隆自身が現代音楽の「響きがキモすぎる」と感じる風潮に異議を唱え、「美しいメロディやハーモニーを取り戻す」ことをコンセプトに作曲している人物です。
彼の音楽は「非常に聴きやすく」、「単なるポップスでは説明できない美しさ」があり、音楽本来の「ワクワクするような魅力」が詰まっていると評価されています。
現代音楽にありがちな難解な響きや無調を避けて、意図的に美しい旋律や和声を取り入れているため、現代音楽特有の響きに抵抗があるという方にこそ、ぜひ最初に聴いてみていただきたい作曲家です。
現代音楽を聴くためのちょっとしたヒント
これらの作品を聴く際に、少しだけ意識してみると新たな発見があるかもしれません。
- 「メロディ」にとらわれない: いつもの音楽のように、明確なメロディを追いかけようとしすぎないでください。
- 「音」そのものに耳を澄ます: どんな音が鳴っているか、音色や響き、音の重なり(「垂直方向の響き」)に注目してみましょう。突然現れる音や、耳慣れないサウンドも、その音楽の一部として受け入れてみてください.
- 背景やコンセプトを知る: もし興味が湧いたら、その曲が書かれた時代背景や作曲家が何を表現しようとしたのか(コンセプト)を調べてみると、より理解が深まることがあります。現代音楽はしばしば、単なる音の羅列ではなく、強い思想やコンセプトに基づいています。
- 繰り返し聴いてみる: 一度で分からなくても大丈夫。人間の耳は順応性があり、繰り返し聴くことで、新しい響きや構成の面白さが分かってくることもあります.
難解?いや、実は面白い 現代音楽の楽しみ方
現代音楽を初めて聴く方にとって、その響きに戸惑うことは自然な反応です。
これまでの音楽で心地よいと感じてきた「調性」や「和音」のルールに沿っていないため、次にどんな音が来るか予想できなかったり、耳慣れない響きに不快感を感じたりすることもあるかもしれません。
しかし、現代音楽には従来の音楽とは異なる面白さや魅力がたくさんあります。
現代音楽を聴く上で大切なのは、まず「正解はない」と考えることです。
作曲家が意図した通りの感情を受け取らなければいけない、というものではありません。鳴っている音そのものを素直に感じてみることが第一歩です。
不協和音やノイズと感じられる音も、それ自体を一つの「音色」として楽しむことができます。
現代音楽はしばしば他の芸術分野と関連が深いため、そのコンセプトや背景にある思想を知ることで、より深く理解し、知的な面白さを感じることができます。
例えば、特定の作曲技法がなぜ生まれたのか、その技法が何を目指しているのかを知ることで、耳で聴く音楽だけでは得られない発見があるでしょう。
聴き慣れない響きも繰り返し聴くうちに耳が慣れてきて、その音楽が持つ独特の美しさや魅力を感じられるようになることがあります。
オペラや演劇を観るように、現代音楽の演奏会を一つの新しい体験として捉え、「この音楽で何が表現されているのだろう」「なぜこんな音が鳴るのだろう」と考えながら聴いてみるのも一つです。演奏者のパフォーマンスや演奏される空間全体を、一つの芸術として楽しむことができます。
音楽は「作品」ではなく「出来事」
現代音楽をより深く理解するための視点として、音楽を単に楽譜や音源といった完成された「作品」として捉えるのではなく、演奏、聴取、作曲といった人々の「行為」や、楽器、空間、録音媒体といった「事物」、そしてそれらを取り巻く人間関係などが相互に結びついて成り立つ「出来事」として捉える考え方があります。
音楽は作曲家が音を作り、演奏家がそれを再現し、聴衆がそれを聴く、といった一方通行の関係だけではありません。
楽器の存在、演奏される場所の響き、聴衆の反応、そしてそれらを経験する個人の内面的な感情など、様々な要素が絡み合って、その瞬間の「音楽」が生まれます。
現代音楽は従来の音楽の枠を超えた表現を追求するため、音そのものだけでなく、演奏方法、演奏される空間、聴衆の参加といった要素が音楽の構成要素として、重要になることがあります。
このように現代音楽は、作曲家の思想、音楽技法の進化、他の芸術分野からの影響、そして音楽を取り巻く様々な要素との関係性の中で発展してきました。
難解と感じられる響きも、その背景や意図を知ることで新しい発見や感動をもたらしてくれる可能性があります。
折あらば、多様で未知なる(アタオカと紙一重な😅)響きの世界に触れてみてください。慣れるとおいしい、くさやの干物。

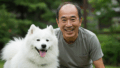

コメント