ジャズの歴史には、数多くの個性的なミュージシャンが存在します。その中でもアルトサックス奏者のソニー・クリスは、独特の音色と表現力豊かな演奏で知られる人物です。
ソニー・クリスの類まれな音色と楽器セッティング
ソニー・クリスの音色は、非常に個性的であると評されます。多くのジャズアルトサックス奏者がハードラバー製のマウスピースを使用する中(フュージョンやロックのプレイヤーは除いて)、彼のサウンドの大きな特徴となっていたのは、セルマー社製のメタル製ジャズモデルというマウスピースでした。このマウスピースは、他のジャズアルト奏者にはほとんど使用例が見られないもので、彼のアルトサックスの音色の個性を決定づけていたと言えるでしょう。この独特なセッティングが、彼のオリジナリティ確立に貢献したと考えられています。
チャーリー・パーカーが及ぼした影響
ソニー・クリスはチャーリー・パーカー没後のアルトサックスシーン、いわゆる「パーカー派」、あるいはパーカーの流れを汲むミュージシャンの一人として位置づけられています。多くのアルトサックス奏者がパーカーに追随した時代背景があるのです。
クリスがパーカー派に連なる存在として語られる一方で、彼のサウンドやスタイルはブルースやハードバップに根ざしており、特にブルースフィーリングや「泣きのサックス」と評される情感豊かな表現力が強調されています。これは単にパーカーの超絶技巧やバップのフレーズを模倣するだけではない、クリス独自の音楽性として評価されています。
クリスの晩年の演奏、特に『サタデイ・モーニング』やその数年前の録音におけるシャープでタイトなサウンドや集中力を指して、「パーカー的なアプローチ」 と表現されることもあります。
彼のこの集中的なアプローチや「完璧」な演奏への追求が、逆に「うまく吹いてやろうという意識」のごとくに捉えられ、パーカーの自然体の演奏と比較して疑問視される側面も示唆されています。
村上春樹氏は『アップ、アップ・アンド・アウェイ』のラナーノーツに、クリスが「うまく吹こうなんて考えること自体、神(パーカー)を冒涜する行為である」と考えていたのではないか、との見解を述べています。パーカーの才能は規格外であり、技術的な完璧さの追求そのものがパーカーへのアプローチとして適切ではない、というニュアンスを含んでいます。クリスはパーカーの技術をそのまま受け継ぐというよりは、パーカーが切り拓いたジャズの表現世界の延長線上で、自身のサウンドと表現力を深めていったという解釈です。
村上氏はクリスが「吹くごとに、年をとるごとにうまくなっていくミュージシャンであった」、また「決して一流の才能をもってその演奏活動を始めたわけではないけれど、遂には一流の域に達した人であった」 と評価しています。天才型で早逝したパーカーとは対照的に、継続的な努力と探求によって自身の音楽を高めていったクリスの特徴を示しており、パーカーの遺産を独自の形で消化し、発展させた結果に対して村上氏ならではの賛辞かもしれません。
インド音楽のラーガの概念がブルースにも通じるという議論は、クリスのブルースフィーリング溢れる演奏を理解する上での参考になります。ラーガがスケールやメロディとは異なる「響き」や「ムード」、演奏家固有の「個性」であるように、ブルースもまた決まった形だけでなく、演奏者の個性によって大きく印象が変わる音楽です。
クリスのユニークな音色と表現力は、テクニックや形式を超えた深い「個性」の表れであり、パーカーが切り拓いたジャズの広がりの中で、彼独自の「響き」を見出した結果と捉えられます。
チャーリー・パーカーは、ソニー・クリスが活動した時代の最も重要なアルトサックス奏者です。直接的な共演の機会もあり、クリスはパーカー派の一人として認識されていました。しかしクリスは、単にパーカーを模倣するにとどまっていません。独自のメタルマウスピースを使用することによる個性的な音色や、ブルースフィーリングを深く追求した表現力、そしてキャリアを通じて向上し続けた演奏技術によって、ジャズ史に独自の足跡を残しました。
彼の音楽的発展はパーカーが提示したモダンジャズの地平の上で、彼自身の内面と探求の結果として形作られたものと言えます。
代表作『アップ、アップ・アンド・アウェイ』
ソニー・クリスは1963年から1965年にかけてヨーロッパで音楽活動を行った後、アメリカに戻り、有名なジャズレーベルであるプレスティッジと契約を結びました。プロデューサーはドン・シュリッテンが務めました。プレスティッジからはオムニバス盤を含めて合計8枚のアルバムをリリースしています。これは彼のキャリアにおいて非常に重要な時期となりました。
ソニー・クリスの代表作の一つである『アップ、アップ・アンド・アウェイ』は、彼のキャリアにおいていくつかの重要な意味を持っています。
プレスティッジ・レーベルでのキャリアにおける位置づけ
『アップ、アップ・アンド・アウェイ』は、プレスティッジからのリリースとしては3作目にあたります。プレスティッジからはオムニバス盤を含め合計8枚のアルバムがリリースされており、この時期は彼の重要な活動期間でした。
選曲における革新性とイメージ確立
このアルバムの最大の重要性は、それまでのアルバムがスタンダード・ナンバー中心の選曲であったのに対し、当時のポップスのヒット曲を積極的に取り入れたことにあります。この選曲が功を奏し、ソニー・クリスは「ポップスナンバーをメロウに吹くアルト奏者」というイメージが広く定着しました。
代表作としての位置づけ
『アップ、アップ・アンド・アウェイ』は、彼の晩年の名作とされる1975年作品の『サタデイ・モーニング』と並び称される代表作です。
日本における特別な重要性
このアルバムは、クリスの死後、1980年にビクターから日本盤LPがリリースされました。この日本盤には、当時まだ作家としてデビュー間もないながら、ジャズ喫茶を経営していた村上春樹氏がライナーノーツを寄稿しています。
村上氏のライナーノーツは、チャーリー・パーカー没後のアルトサックス奏者たちを落語仕立てのユーモラスな筆致と深いジャズ知識で描いた名文として評価されており、このアルバムが日本のジャズファンに特別な文脈で語り継がれる要因の一つとなりました。
『アップ、アップ・アンド・アウェイ』は、ソニー・クリスがプレスティッジ期に商業的な成功と新たなイメージを確立した作品です。特に日本では、著名な作家によるライナーノーツを通じてその存在が広く知られるきっかけとなった、キャリア上および文化的にも非常に重要な代表作と言えます。
多様な楽曲へのアプローチと演奏スタイル
ソニー・クリスはポップスやスタンダードだけでなく、ブルースやバラードでの表現力に定評がありました。彼の演奏スタイルは「歌いっぷり」が良いと評され、ブルーノートやコブシを用いた「むせび泣き」のような表現も特徴的です。
有名な楽曲「サニー」の演奏では、オリジナルよりも速いテンポで演奏したり、ジャズロック風のリズムからスイングに切り替えたりするなど、楽曲によって多様なアプローチを見せます。また、「エンジェル・アイズ」での演奏は、彼の技術と音色の良さが際立っていると評価されています。
彼の演奏における「個性」や「表現力」の重要性は、インド音楽の「ラーガ」の概念と比較することで、より深く理解できるかもしれません。ソースの一つによると、ラーガは「抽象的なサウンドの捉え方」であり、スケールやメロディとは異なる、響きとして存在する個性やムードのようなものです。真の巨匠は一つの音を鳴らすだけでそのラーガを聴き手に感じさせることができるほど、その個性が強いとされます。
この概念はブルースにも当てはまると述べられており、ブルースもまた決まったスケールやメロディだけでなく、演奏者の個性によって印象が大きく変わる音楽だからです。ソニー・クリスがブルース演奏で高く評価され、そのユニークな音色と表現力で知られるのは、まさにこのような、スケールやメロディを超えた「響き」や「ムード」、つまり演奏家固有の「個性」を強く表現できたからだと言えるでしょう。
彼は様々なスタイル(ポップス、ジャズロック、ファンクなど)にも適応しようとしましたが、その根底には彼独自のサウンドとブルースやハードバップに根差した表現力がありました。
名だたる共演者たち
ソニー・クリスのアルバムには、多くの優れたミュージシャンが参加し、彼の演奏を支えています。『アップ、アップ・アンド・アウェイ』には、シダー・ウォルトン(ピアノ)、タル・ファーロウ(ギター)、ボブ・クランショウ(ベース)、レニー・マクブラウン(ドラムス)が参加しています。
名盤3選
ソニー・クリスの代表作『アップ、アップ・アンド・アウェイ』以外にも、重要な作品がいくつかあります。ソースの情報に基づいて、特におすすめできる3枚の名盤は以下の通りです。
『サタデイ・モーニング (Saturday Morning)』
このアルバムは、『アップ、アップ・アンド・アウェイ』と並び称される代表作であり、彼の晩年1975年の記録です。
70年代ハード・バップ・リバイバルの動きの中で再評価されたアルバムであり、その中でも「極め付き」とまで評されています。
プロデューサーは『アップ、アップ・アンド・アウェイ』と同じドン・シュリッテンです。
このアルバムでは彼の演奏におけるピッチの問題が完璧に解決されており、タイトなタイム感、ニュアンスやアーティキュレーションの明瞭さ、フレージングの曖昧さの排除、そして何よりメッセージの発露の明確さが感じられると評されています。日本ではジャズ喫茶で大ヒットしました。
『ゴー・マン! (Go Man!)』
これもソニー・クリスの重要なアルバムとして、度々言及されています。クリスの魅力が詰まった作品です。
「サマータイム」、「メモリーズ・オブ・ユー (Memories Of You)」、「ブルー・プレリュード (Blue Prelude)」など、聴きどころがいっぱいです。ソニー・クラークがピアノで参加しています。
このアルバムはチャーリー・パーカーの影響を受けつつも、クリス独自の世界観を築き始めた時期の演奏が聴けます。
『クリスクラフト (Criss Craft)』
『サタデイ・モーニング』と同じく、1975年にミューズ・レコードからリリースされたアルバムです。ギターが入ったクインテット編成の作品です。
ホレス・タプスコット作の名曲「ディス・イズ・フォー・ベニー 」の演奏が高く評価されています。陰りのある曲想がクリスの哀感を引き出し、よりブルージーな表現をもたらしています。この曲は『アップ、アップ・アンド・アウェイ』にも収録されています。
これらのアルバムは、ソニー・クリスの音楽を理解する上で非常に重要な作品群と言えます。特に『サタデイ・モーニング』は、晩年の彼の到達点を示す名盤として高い評価を得ています。
日本での人気と悲劇的な晩年
ソニー・クリスは、1977年に初の来日公演が予定されていました。当時、アルバム『サタデイ・モーニング』が日本のジャズ喫茶で大ヒットしており、複数のコンサートが企画されます。当時の日本では、ジャズ喫茶がモダンジャズ鑑賞の情報発信・交換の中心地としての役割を果たしていました。クリス自身も、プロモーターが彼の「演奏したい曲のみ」という条件を快諾したことから、この日本公演を非常に楽しみにしており、楽器を吹きながら小躍りするほど喜んだと伝えられています。
しかし、来日公演の数日前の1977年11月19日朝、彼は拳銃による自殺を遂げます。死因は胃がんによる激痛と判断されています。しかし、来日を心待ちにしていた様子から自殺であることに疑問を呈する声や、様々な風説が流布されます。『サタデイ・モーニング』で彼が到達した芸術的な深みを考えると、なぜ彼が自死を選んだのか、理解しがたいのは確かです。
ソニー・クリスはその個性的な音色、ブルースフィーリング溢れる表現、そして円熟期に到達した高い演奏技術で、ジャズアルトサックスの世界に確かな足跡を残しました。彼の多様な作品を通して、その魅力的な世界に触れてみてはいかがでしょうか。

幼少期、家に風呂がありませんでした。母親と行く銭湯、湯上りに買ってもらうコーヒー牛乳は、幼児の私にとって至福の時でした。
風呂上がりの火照った体に、甘くよく冷えたコーヒー牛乳をぐびぐび入れれば、快楽にも似たのどごしが全身を駆け巡ります。
銭湯と瓶のコーヒー牛乳は記憶の中で一体化していて、それ以降に飲んだ紙パックや缶のそれは、同じ飲み物とはいえません。
純度100%、混じりっけなしの「気持ちいい」体験は、銭湯というハレの場と、お神酒代わりのコーヒー牛乳の二つが交わることで実現したのです。
ソニー・クリスのアルトは、まさに銭湯で飲むコーヒー牛乳です。「気持ちいいな」「おいしいな」が、知識や理屈抜きに五臓六腑をしみわたります。
もちろん、湯上りのチャーリー・パーカーだって中々乙なもんかもしれません。ただ”大吟醸”をたしなもうと思えば、なんせお高いし、しっかり味わねばと正座の一つしたくなります。あの当時、たしかコーヒー牛乳は20円だったもんな。
この特別な飲料は、あくまで値段は庶民に優しく、それなのに最上の喜びを与えてくれたのです。
左手を腰に当て、何も考えず立ったまま一気に飲み干す爽快感。それこそがソニー・クリスならではの気持ちよさ、おいしさなんであります。


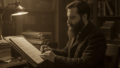
コメント