悪口や陰口は、私たちの日常生活や人間関係においてしばしば遭遇する問題です。なぜ人は他人を悪く言ってしまうのでしょうか。その背景には、進化の過程で培われた特性や、現代社会の要求とのずれ、そして複雑な心理が関わっています。言われた側だけでなく、言う側や周囲にも様々な影響を及ぼします。
悪口と陰口の定義と違い
まず、悪口と陰口の違いについて確認しておきましょう。
悪口(わるくち) とは
人を悪く言うこと、またはその言葉を指します。特定の人物を不快にさせたり、傷つけたりする目的で悪意を持って発せられる言葉のことです。相手をけなしたり、侮辱したり、品位を傷つけたりするような内容が含まれます。
陰口(かげぐち) とは
当人のいないところで、その人の悪口を言うことを指します。陰口は悪口の一種であり、本人に直接言う場合は陰口には当たりません。直接言えば悪口、陰で言えば陰口ということです。
人が悪口や陰口を言う理由:進化、心理、社会
人が悪口や陰口を言う背景には、様々な要因があります。
進化と起源
進化心理学の観点からは、悪口や噂話にはヒトが進化の過程で獲得してきた生得的な特徴が関係しています。噂話は太古の時代、類人猿が行っていた「身づくろい(グルーミング)」が起源という説があります。これは個体間の絆を深め、集団内の協力関係を維持するための手段でした。
言葉の獲得により「身づくろい」は、より効率的に多くの個体と情報を共有する「直接話す」という形に進化しました。 集団生活においては、資源を独占したり協力体制を乱したりする「裏切り者」が出現する可能性があります。このような裏切り者を早期に発見し、集団の崩壊を防ぐためのシステムとして、「うわさ」が機能したのだと考えられます。
村人が怪しい動きやずるいことを見聞きすると、その人のグチを言い始めます。それが噂となって広まり、裏切り者がすぐにバレるだけでなく、悪いことをしないように牽制する役割も担いました。このようにグチは、「敵を炙り出す役割」も担っていたのです。ゴシップは「最古のSNS」と表現されることもあります。

しかし、現代の文明社会が求める要求と、遠い昔の進化の過程で身につけた心理や身体的特徴には、大きなずれが生じています。現代では、スマートフォンの普及によりテキストによる会話(LINEなど)が、場所や時間を選ばず瞬時に多くの人と言葉を交わせる「最強に効率的なうわさ話の手段」となり得ます。これはかつての「身づくろい」が、凄まじい勢いで進歩した形とも言えます。
心理的な理由
心理学的な観点からは、悪口や陰口を言う人の心理は多様です。
コミュニケーションツール
悪口や陰口は共通の話題として利用されやすく、コミュニケーションを円滑にするためのツールとなることがあります。
秘密の共有
人前では言いにくい悪口や陰口を共有することは、特別な秘密を分かち合うことになり、関係性を深める鍵となります。これにより、互いに特別な存在であるかのような感覚や、一体感・連帯感が生まれます。秘密の共有は単純接触効果、返報性の法則、類似性の法則、社会的浸透理論といった心理法則と結びつき、「特別な関係」への変貌を促します。
共通の話題での団結
共通の敵(悪口や陰口の対象)を設定することで、自分たちのグループとそれ以外のグループを分け、グループ内での一体感や団結する安心感を得られます。

他者を下げて自己防衛
自分に自信がなく不安な場合、自分よりも注目されている相手の価値を下げることで、自尊心を守ろうとする自己防衛の心理が働きます。
勝ち負けのマウント取り
勝ち負けや優劣を判断基準としている場合、自分が上であることを誇示するためにマウント取りを行うことがあります。これはプライドや劣等感から生じます。
快楽とストレス解消
悪口を言うと、やる気ホルモンであるドーパミンが分泌され、快感をもたらします。他者の悪口を言うことで相対的に自分の価値が高まったように感じ、ストレスを解消する手段となるのです。しかし、これはあくまで一時的なものであり、錯覚である可能性も指摘されています。欲求不満が高まり、怒りやイライラの情動を抱えた際に、手っ取り早く発散する方法として攻撃行動(悪口を含む)が選択されるという「情動発散説」があります。
自分が言われないための忖度
悪口を言っている人に合わせ、自分が悪口の対象にならないように忖度し、一緒になって悪口を言ってしまうケースがあります。人によって罪悪感が生じ、ストレスを抱えることになります。
劣等感
結局のところ、悪口や陰口が多い要因は劣等感、僻み、妬みである場合が多いとされます。悪口を言うことは、自身が劣っていることを認めていることとも言えます。
悪いことという自覚がない
悪口や陰口を言う当人に、悪いことをしている自覚はありません。むしろ自分の悪口こそが正当な評価だと、本気で主張するケースも見られます。
ストレス
思い通りにならないことや対人不安、人間関係のストレスなどを感じている人が、そのストレスを解消するために悪口を言うことがあります。傾向として、自分より立場が弱い人や自分の方が正しいと思える相手にぶつけます。過去のトラウマや嫌な思い出が影響している場合もあります。

悪口・陰口を言う人の傾向
悪口と陰口では、それを言う人の傾向に違いが見られることがあります。
悪口(直接言う人)の傾向
プライドが高い、自信家、気が強い、正義感が強い(純粋なものか歪んだものか見極めが必要)、短気。
プライドを傷つけられると、攻撃的になります。言い返されても構わないという(変な)自信があるらしく、好戦的に仕掛けたり、物事の優劣を勝ち負けで判断し、自分の正しさを主張したり、感情的にぶつけたりする傾向があります。
陰口(陰で言う人)の傾向
劣等感が強い、自信がない、気が弱い、自分が注目されたい、卑屈。
劣等感から、自分より優れている人に妬みを抱きます。少しの落ち度を大げさにして陰口を言ったり、自分や自分の意見に自信がなく直接言えないため陰口をたたいたりします。他人の評価が気になっても、気が弱く真っ向から対峙したくなかったり、注目される人への嫉妬心から評判を落とそうとしたりします。自分を評価しない仕組みや制度に不満を抱き、陰口を言うことで仲間を作って安心を求めたりする傾向です。陰口を言う人は、仲間を増やしたがるようです。
悪口や陰口がもたらす影響
悪口や陰口は、関わる全ての人に影響を与えます。

言われた側への影響
人間関係の悪化
陰口は本人に伝わってしまう可能性が高く、「本人が聞いていないからバレないだろう」という考えは通用しません。陰口が伝わると、言った人と言われた人の関係が悪化し、そうなれば後から改善される余地はほぼありません。
精神的な苦痛
悪口や陰口によって自尊心を傷つけられ、苦しい思いをします。周りから見れば些細なことでも、言われた本人には大きな問題となります。精神的なダメージは、パワハラやモラハラに該当するケースもあり、放置するとエスカレートする恐れがあります。悪評について親切を装って伝えられる場合、実際には感情を乱されている可能性があります。言葉の暴力は精神疾患を引き起こすこともあり、これは傷害罪に該当する可能性さえあります。

記憶への影響
悪口を言った方はすぐに忘れますが、言われた側は死ぬまで忘れないほど、傷つくことがあります。「夢で人を殺す夢を見てしまった」と妻が言ったことに対して、「君は人を殺していてもおかしくない人間だよね」と返した夫。何度も繰り返された心無い夫の言葉から、妻は離婚を決意したそうです。こうしたエピソードは、言葉の暴力がもたらす深い傷を示唆しています。
噂の歪曲と拡散
噂は伝達されるごとに内容が削ぎ落とされたり(平準化)、特定の要素が誇張されたり(強調化)、受け手の既有観念に合わせて変形(同化)されたりして歪められ、誤情報が広がりやすくなります。特に悪意のある噂は、インパクトが強いため誇張されやすく、本人が知る前に職場中に広まっていることがあります。面白おかしく改変されると、さらに伝えたくなる気持ちを引き出します。
言う側への影響
人間関係の悪化
陰口を言う人は、言われた人との関係が悪くなるだけでなく、陰口を聞いた人からも「この人は他の人の悪口も陰で言っているかもしれない」と疑われ、信用を失う可能性があります。いつも陰口を言っている人の評判が良くなることはありません。行き過ぎた陰口は、逆にその人の評価を悪くします。
時間の無駄
陰口を言ったりアンチコメントをしたりする時間は、何もメリットがなく、貴重な時間の無駄です。
自分自身への影響
悪口を言えば言うほど、その人に対する嫌悪感が強まり、自身の心が荒れ、自分自身が苦しくなります。悪口や陰口を言うことは、長い目で見れば失うものが多く、やめる方が良いと指摘されています。
科学的な理由から、「悪口を言う人」には最低最悪の人生が待っている可能性や、認知症リスクが3倍、寿命が10年縮まる可能性も指摘されています。
社会的な影響
口論や侮辱が罵り合いに発展し、傷害事件や殺人事件につながることもあります。
特にインターネットやSNS上での誹謗中傷は、匿名性の高さから容易に行われやすく、真実であっても名誉毀損が成立し得る危険な行為です。警察への被害相談件数は年々増加しており、被害者の中には精神的苦痛で自殺・自殺未遂に至る者もいます。
SNSでの悪質な書き込みで著名人を自死に追いやることを、韓国などで「指殺人」と呼ぶ俗語が存在します。政府も注意喚起を行ったり、侮辱罪の厳罰化といった法改正が行われたりしています。しかし、海外SNS企業の捜査協力拒否など、問題解決には課題も多い状況です。
悪口・陰口への対処法
悪口や陰口に直面した際の対処法や、自身が悪口を言ってしまう傾向がある場合の改善策です。
言われた側の対処法
悪口や陰口を言われても、傷つかないための心がけや対処法があります。
気に留めない
気になっても、感情的にならず冷静に対処することが重要です。相手の思考をコントロールすることは難しいため、「悪口をやめてほしい」と思っても、その気持ちが相手に伝わる可能性は低いと認識することから始まります。
俯瞰して見る
今起きている事柄を客観的に整理し、俯瞰して捉える視点を持ちましょう。具体的な悪口の内容、状況、相手がなぜそういう態度なのかなど憶測を排除して、事実だけを観察します。

自己の内省
言われたことに対して、自身がどう感じたかを確認し、その相手と今後どのような関係でいたいのか(歩み寄りたいか、疎遠でも構わないかなど)自分の気持ちを整理します。相手への「観察」と自分への「内省」の両面を持つことで、俯瞰的な視点が得やすくなります。
信頼できる相手へ相談
問題を一人で抱え込まず、内外の信頼できる相手に相談しましょう。アドバイスを得られる可能性や味方になってくれる場合があり、話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなります。ただし相談相手には、問題の対象者に対し応戦しないようにとの確認が必要です。あくまで「困っているので相談したい」というスタンスが大切です。
本人に直接話す
悪口や陰口が明らかな誤解に基づいている場合は、本人と直接話すことも一つの方法です。
環境を変える
どうしても状況が改善しない場合、パワハラ・モラハラに該当するようなエスカレートが見られる場合は、環境を変えることを検討すべきです。仕事であれば転職も選択肢の一つであり、その際は信頼できるキャリアアドバイザーに相談することも有効です。
必要以上に自分を卑下しない
悪口・陰口は言う側に問題があることを理解し、必要以上に自分を卑下したり、自責の念に駆られたりしないことが大切です。憐れむべきは、悪口・陰口でしか思いを表明できない相手なのです。
悪口を言う側がやめるための対処法
もし自身が悪口を言ってしまう傾向があり、それをやめたいと考えているのであれば、以下のような方法が考えられます。

怒りをうまく解消する
悪口は怒りを鎮める行為であるため、別の方法で怒りをうまく解消できれば、悪口を言う必要がなくなります。
視点を広げる
「他人は私を喜ばせるために生きているわけではない」「人はあくまでも自分の都合で生きているものだ」といった考え方をすることで、怒りの原因に対する認識を変えることができます。期待を押し付けないことも重要です。
悪口と本音を区別する
悪口は自分の気持ちを「毒々しく、怒りを込めて表現したもの」であり、気持ちそのものではありません。悪口という表現方法を使わなくても、自分の本当の気持ち(本音)を人に伝えることができる、その気づきが大切です。
「私」を主語にして本音を表現する
気持ちを吐き出したい時は、「あの人はあんなことを言った(した)、だからあいつは〇〇(悪口)だ」と言う代わりに、「あの人があんなことを言った(した)、だから私はとても〇〇(自分の気持ち)だ」と、「私」を主語にして自分の感情を表現してみましょう。聞く側にしても、悪口より本音を聞く方が共感しやすく、共感してもらえれば自分も楽になります。悪口を言いたくなる時は、自分が苦しい時だと自覚しましょう。
悪口や陰口を聞かされた側の対処法
悪口や陰口を直接言われるわけではなくても、聞かされて不快な思いをすることもあります。
反応せず同調しない
悪口を聞かされている時に「えー!それは酷いですね!」や「え、それは私もイヤだなぁ」のように反応し、負の言葉に同調することは、自身も一緒になって悪口を言っているような感覚になり、居心地の悪さを感じる原因となります。反応するのをやめ、「んー」や「へー」といった曖昧な受け答えだけをするようにすると、居心地の悪さが軽減されます。
一歩引いて線引きする
否定も肯定もせず、「この話に興味ないです」という雰囲気を漂わせることです。一歩引いて、話を聞きましょう。「この人はそう感じているんだ」「私はそんなこと1ミリも思っていない」と、心の中で線引きするのが良い方法です。
噂の模倣の連鎖を断ち切る
噂話は模倣の連鎖によって広がるため、自分がそこで噂を止める、つまり模倣の連鎖を断ち切ることが噂の影響を最小限にする鍵となります。噂を聞いた際に、その真偽や自分にとって伝える必要性があるかを吟味するのです。

歴史の中の悪口
悪口や言葉の暴力は、現代社会に限った問題ではなく、歴史の中にもその存在や法的な位置づけが見られます。
日本の鎌倉時代には「悪口の咎」というものがあり、鎌倉幕府の裁判手続きにおいて重要な規定でした。御成敗式目第12条では、一般的な悪口には情状に応じて流罪や召籠といった制裁を定め、特に裁判の場での悪口に対しては厳しい処罰が科されました。
鎌倉時代の裁判における悪口の罪は単なる言葉のやり取りにとどまらず、土地の帰属などに関わる重大な結果をもたらし得るものでした。裁判で敵方の言葉尻を捉えて悪口罪の適用を求めるケースが急増した背景には、それが認められれば道理のない訴訟でも勝つことができたため、「悪口さがし」が熱心に行われたのです。
当時の社会では、身分的な蔑称(例えば「若党」や「甲乙人」など)も悪口として問題視されることがありました。さらに、「母開に及ぶ」「おやまけ」といった性的な事柄に触れる言葉が悪口として使われた事例が確認されています。
鎌倉幕府がこうした悪口を厳しく処罰したのは、喧嘩や敵討ちといったより大きな争いへの発展を未然に防ぐため、また法廷の秩序を維持するためであったと考えられています。ただし、悪口が争点とされる場合でも事実認定は慎重に行われており、一概に感情論だけで判断したわけではないようです。
現代社会と悪口・陰口
現代社会、特にインターネットやSNSの発達は、悪口や陰口の形態・影響を大きく変えました。
匿名性の高いネット空間では、無思慮な誹謗中傷が容易に行われ、その影響は瞬時に広範囲に及び、被害者にとって深刻な問題となっています。法整備も進められてはいますが、インターネット上の誹謗中傷は依然として大きな課題です。
現代の職場や学校におけるいじめにも、悪口や陰口は深く関わっています。これらは情動発散の手段として他者を攻撃する行動の一形態と考えられており、人間の根源的な問題の一つであると言えます。
まとめ
悪口や陰口は、進化の過程で培われた特性、複雑な心理、そして社会的な要因が複合的に絡み合って生じる人間の行動です。それはコミュニケーションのツールとなり得たり、集団内の絆を深めたりする機能を持つ側面もあります。しかし多くの場合、関係を悪化させ、言われた側だけでなく言う側の心も傷つけ、深刻な精神的苦痛や社会問題を引き起こします。
歴史的にも悪口が問題視され、法的に規制されていた時代があることからも、これは普遍的な人間の課題と言えます。悪口や陰口の問題に適切に対処するためには、その背景にある心理やメカニズムを理解し、言われた側としては冷静な対処法を講じ、言う側としては自身の心理状態を理解し、別の方法での感情表現を学ぶことです。


悪口・陰口は、群れの中で生き残るための本能的な仕組みであり、悪口を言うことで気持ち良いと感じるのも、太古に集団でのマウントが重要だった頃、人間にプログラムされた可能性があります。
現代では必ずしも生存に直結しない無駄な情報が多いのですが、脳がアップデートされていないため、相変わらず様々な情報に反応してしまうのです。
これは「脳の設計ミス」や、「進化の罠にハマってる」状態とも表現されます。
「これから人の悪口を言うぞ」と意識してやる人は、ほとんどいません。他人が嫌がる行動を無意識にとっていると自覚すれば、改善も期待できそうですね。

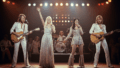

コメント