不朽の名曲への扉を開く
ドミートリイ・ショスタコーヴィチの交響曲第5番は数ある彼の作品の中でも最も広く知られ、愛されている一曲です。多くのリスナーにとってこの曲は、ショスタコーヴィチの世界への扉を開く登竜門のような存在と言えるでしょう。
この交響曲が書かれた背景には、作曲家自身の苦悩や当時の社会情勢が深く関わっています。単なる音楽としてだけでなく、その背景にあるストーリーやメッセージを知ることで、より深く作品を理解し、楽しむことができます。
この記事では交響曲第5番が生まれた激動の時代から、作品に込められたかもしれない様々なメッセージ、そして数々の名演まで、この不朽の名曲に隠された重層的な魅力に迫ります。
激動の時代を生きた作曲家の試練
ショスタコーヴィチが生きた20世紀のロシアは、ソビエト連邦という体制の下、芸術家にとって非常に困難な時代でした。特に、最高指導者スターリンによる大規模な政治弾圧、通称「大粛清」の時期には、多くの人々が理不尽な理由で逮捕され、命を落としました。この災厄は政治の世界だけでなく、文化や芸術の分野にも及びました。
ソビエトが芸術家に求めたのは、「社会主義リアリズム」という唯一の表現方法でした。これは、国の偉大さや革命、指導者を賛美するような、誰にとっても分かりやすく、毒にも薬にもならない音楽を推奨するものでした。
才能あふれる若きショスタコーヴィチは、体制の要求とは異なる、不協和音を多用した交響曲やオペラを発表し、大きな注目を集めていました。しかし、1936年、彼のオペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」がソビエト共産党の機関紙「プラウダ」で「音楽のかわりに荒唐無稽」、バレエ音楽「明るい小川」が「バレエの嘘」と激しく批判されます。これは単なる芸術批評ではなく、作曲家自身を「体制への反逆者」と見なす政治的な圧力でした。
かつて「モーツァルトの再来」とまで称賛されたショスタコーヴィチは、この批判によって一転して困難な立場に追い込まれます。文化を堕落させる有害人物とされ、あらゆる公の場で非難され、自己批判を強いられました。さらに、この時期には彼の友人や親類が次々と逮捕・処刑されていくという悲惨な状況に直面しました。
この厳しい現実の中で、ショスタコーヴィチは芸術家としての基盤を失う危機に瀕し、次の作品で名誉を回復する必要に迫られていました。事実、批判に先立って作曲していた意欲作交響曲第4番は、作曲者自身の判断で初演が中止されています。
このような状況下で、ショスタコーヴィチは新たな交響曲の作曲に取り掛かります。それが後に彼の代表作となる、交響曲第5番です。
「正当な批判への回答」 勝利か、それとも強制された歓喜か
1937年に作曲された交響曲第5番は、批判された前衛的な作風から大きく転換し、より分かりやすい、伝統的な4楽章形式を採用した純器楽の作品となりました。この曲は革命20周年という記念すべき年に初演され、聴衆から熱狂的な歓迎を受けます。
ソビエト作家同盟議長のアレクセイ・トルストイは、この作品を「社会主義リアリズムの最も高尚な理想を示す好例」として絶賛しました。これによりショスタコーヴィチは一時的に名誉を回復し、危地を脱することに成功します。この作品は、公式には「正当な批判に対する一人のソビエト芸術家の実際的かつ創造的な回答である」という批評をもって評価され、これが非公式な副題のように広まりました。
この「正当な批判への回答」という言葉の裏には、様々な思いが隠されていたのではないかという憶測が生まれます。初演後、ショスタコーヴィチ自身が友人の指揮者、ボリス・ハイキンに「フィナーレを長調のフォルテシモにしたからよかった。もし、短調のピアニッシモだったらどうなっていたか。考えただけでも興味深いね」と、皮肉めいたコメントを残した逸話があります。これは彼が体制の要求に応える形で、本心とは異なる音楽を書いた可能性を示唆しています。
ショスタコーヴィチの死後に出版された暴露本「ショスタコーヴィチの証言」(真偽には論争がありますが)の中では、この交響曲のフィナーレが「強制された歓喜」であると述べられていたことが明らかになります。表向きは体制を賛美し、勝利を祝うかのような音楽でありながら、内面では苦悩や抵抗の精神を隠していたという解釈を生みました。
このように交響曲第5番は、初演当時から公式の解釈と、作曲家本人の発言やその後の証言、研究によって示される多様な解釈が存在しています。この作品が本当に伝えたかったことは何なのか、その真意は未だに謎に包まれており、聴く人それぞれが自由に物語を紡ぐことのできる「オープンな書物」と言えるでしょう。
ちなみに日本では、この作品に「革命」という副題が付けられることがあります。ショスタコーヴィチ自身が命名したものではなく、欧米では一般的でありません。作品番号がベートーヴェンの交響曲第5番「運命」と同じであることから、ソビエト当局がベートーヴェンのような力強い勝利の交響曲を期待していたという背景はあります。作品自体は最初から最後まで、前衛的な要素には薄い曲となりましたが、それでも十二分に素晴らしい名曲です。
古典形式に秘められた内面の物語 各楽章の聴きどころ
交響曲第5番は、伝統的な4つの楽章で構成されています。全体で約45分の演奏時間です。それぞれの楽章にはショスタコーヴィチの複雑な内面や、当時の社会状況が反映されていると考えられます。
第1楽章 モデラート アレグロ ノン トロッポ
第1楽章は、モデラート指定の静かな序奏で始まります。弦楽器によるカノン風の主題は、まるで内に秘めた不安や葛藤のささやきのように聴こえます。この楽章には、交響曲には珍しいピアノが使われています。続くアレグロ・ノン・トロッポの部分では、弦楽器と金管楽器が激しく対話し、内面に渦巻く怒りや緊張が一気に爆発するような音楽が展開されます。マーチ風の力強い部分も登場します。全体を通して激しい曲調ですが、最後は消え入るように静かに終わります。ここでは、チェレスタの音色が聴こえます。
第2楽章 アレグロ
第2楽章はスケルツォ楽章です。軽妙なリズムの中に、どこか皮肉や不安が漂っています。低弦楽器や木管楽器の断片的なモチーフは、暗い運命を予感させるかのようです。単なる陽気な舞踏曲ではなく、「これは本当の喜びではない」と感じさせる要素が盛り込まれています。戯けたようなヴァイオリンのソロも印象的です。『カルメン』第1幕9場「Tra la la la la la la la わたしの秘密は自分で守る、ちゃんと自分で守るさ」の引用があります。
第3楽章 ラルゴ
この楽章は、交響曲の中でも特に感動的で印象的な緩徐楽章です。ここでは金管楽器や打楽器は一時的に休み、弦楽器と木管楽器が中心となって、深い哀悼と瞑想の世界が描かれます。初演時にこの楽章を聴いて、聴衆がすすり泣いたという逸話も残っています。
失われた友人や苦悩する人々への哀悼が込められているという解釈もあります。弦楽セクションによるレガートで厚みのある悲痛な響きが特徴で、味わい深いサウンドを聴くことができます。木管楽器のソロも美しく、特に木管ソロの一部ではチェレスタが伴奏に使われます。ハープの音色も効果的に用いられています。
第3楽章の楽器編成は金管楽器と打楽器を休ませ、弦楽器と木管楽器を中心に構成されています。具体的には弦楽器全般、オーボエ、チェロ、ヴァイオリン、フルート、クラリネット、チェレスタ、ハープ、そして一部でピアノの低音が使われています。
第4楽章 アレグロ ノン トロッポ
最終楽章はフィナーレです。一聴すると華やかなファンファーレと打楽器の激しいリズムで締めくくられ、体制への賛美や勝利を祝うかのような印象を与えます。編成も大きく、多彩な打楽器や管楽器が登場し、非常にダイナミックで”かっこいい”音楽です。特に冒頭のスピーディでスリリングな部分や、スケールの大きな終わり方は人気のある要因となっています。
しかし、この楽章には単純な「歓喜」だけが込められているわけではないという見方があります。ある批評家はこれを「強制された歓喜」と評し、作曲家が内心では苦悩や皮肉を感じていたことが表出していると指摘しています。フィナーレの急激な転調や繰り返される金管の強烈な主題は、政治的圧力下の内面の葛藤や、自由を求める闘志の現れとも解釈されます。
この楽章の聴きどころの一つに、弦楽器による「ラ」の音が延々と繰り返される箇所があります。この「ラ」は、ロシア語で「リャーリャ」と発音されるため、別れた愛人の名「リャーリャ」を叫んでいるという説があります。最後の部分ではティンパニの連打に重ねて大太鼓が鳴らされ、大きな迫力で曲が閉じられます。
作品に秘められたメッセージを探る
交響曲第5番には、政治的な背景や公式の解釈だけでは捉えきれない、作曲家の個人的な思いや隠されたメッセージが込められているのではないかという議論があります。
その一つが愛人リャーリャ(エレーナ・コンスタンチノフスカヤ)の存在です。ショスタコーヴィチはこの交響曲を作曲する数年前に、音楽祭で通訳をしていた当時20歳のエレーナと出会い、激しい恋に落ちました。彼女に宛てた手紙からは、強い情熱と愛が伝わってきます。エレーナはその後スペインに移り別の男性と結婚しますが、後にカルメンと名を変えています。
交響曲第5番には、フランスの作曲家ビゼーの歌劇「カルメン」から「愛!」というモットーや、「ハバネラ」のメロディーが引用されていることが知られています。特に第1楽章の練習番号29あたりからは、フルートとホルンでカノン風に「カルメン」のハバネラの旋律が引用されています。この引用は唐突に現れ、作品の中で不釣り合いに感じられるため、風刺的な意味合いが込められているのではないかという見方があります。オペラ「カルメン」終幕でのホセのアリア「おれは許さないぞ!」の旋律も引用されており、この引用が、愛人リャーリャへのメッセージであるという説もあります。
さらに、第4楽章ラストで弦楽器によって252回も繰り返される「ラ」の音は、前述のようにロシア語で「リャ」と発音されることから、別れた愛人「リャーリャ」の名を叫んでいるという説があります。音楽評論家のマイケル・スタインバーグは、このコーダをゆっくりとしたテンポで演奏するとハバネラのテンポに近くなり、まるで愛人の名を叫んでいるように聴こえる、と指摘しました。
ショスタコーヴィチは交響曲第5番の作曲直前に、個人的な感情を歌った「プーシキンの詩による四つの歌曲」を作曲しており、この歌曲からも第3楽章などで引用が見られます。これらの引用と愛人リャーリャとの関係性、そして作品全体の構成や表現を考えると、この交響曲には体制批判だけでなく、作曲家の個人的な苦悩や愛、そして生への執着といった人間的な「業」のようなものが複雑に絡み合って表現されているという見方も可能です。
これらの解釈の真偽は、定かでありません。しかし、このように多様な可能性を秘めていることが交響曲第5番を単なる歴史的な遺物ではなく、今なお多くの人々を惹きつけ、様々な「発見」を与えてくれる作品たらしめているのかもしれません。
個性豊かな名演の世界 おすすめの聴き比べ
ショスタコーヴィチの交響曲第5番は、その多様な解釈が可能であるからこそ、指揮者やオーケストラによって様々な演奏が生み出されています。同じ楽譜からこれほどまでに異なる表情が現れるのかと驚かされることでしょう。
ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団
この曲の初演を務めたのは、エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮、レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団です。ショスタコーヴィチは初演のリハーサルにも参加し、指揮者と意見交換をしながら演奏を作り上げていきました。初演者による録音は、作曲家が意図した音楽に触れる上でリアリティがあると言えます。
ムラヴィンスキー盤は、その圧倒的な迫力と白熱した演奏が特徴です。特に晩年の録音(1984年など)は、高音質で円熟した演奏を聴くことができます。一方で1960年代の録音では、レニングラード・フィルの直線的でざらざらとしたいかにもソビエトらしい骨太なサウンドと、鳥肌が立つような猛進ぶりが味わえます。多くのファンにとって、まず聴いておくべき定番と言えるでしょう。
バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック
レナード・バーンスタインはこの曲を複数回録音していますが、特に1959年、ニューヨーク・フィルハーモニックとの最初の録音が有名です。バーンスタインらしい切れ味鋭く、シャープで速いテンポの演奏が特徴です。全体的にスピード感があり、特に第4楽章のラストは熱狂的な盛り上がりを見せます。第1楽章の冒頭の迫力や、マーチ風の箇所の颯爽とした音楽も魅力的です。一方で、第3楽章は遅いテンポで、弦楽セクションの厚みのある響きが味わい深く、神妙でシリアスな音楽を聴かせます。ダイナミックでスリリングな演奏を求める方におすすめです。
ネルソンス指揮 ボストン交響楽団
アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団による2015年の録音は、比較的新しい録音で音質が非常に優れています。壮大なスケールを持ちながらも、細部まで丁寧に作り上げられた質の高い演奏です。弱音部には他の録音では聴き取れないような繊細な音楽があり、発見があります。ボストン交響楽団の色彩豊かな美しい響きを、存分に味わえる演奏です。
コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団
キリル・コンドラシン指揮モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団による1964年の録音も、隠れた名盤として知られています。コンドラシンらしい切れ味の鋭い、密度の濃い演奏です。全体的に速めのテンポで進みますが、第1楽章のドラマを存分に味わえる素晴らしい演奏と言えます。冒頭から鳥肌が立つような集中力の高い演奏は、聴き始めたら止まらなくなる魅力を持っています。
その他の注目盤
他にもダイナミックで熱気あふれるネーメ・ヤルヴィ指揮 スコティッシュ・ナショナル管弦楽団盤、品格高く純音楽的なアプローチのベルナルト・ハイティンク指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団盤、重厚で凍てついた表現が印象的なロストロポーヴィチ指揮 ワシントン・ナショナル交響楽団盤、音質の良さとオケの高いクオリティが光るマンフレート・ホーネック指揮 ピッツバーグ交響楽団盤など、数多くの素晴らしい録音があります。N.ヤルヴィと日本フィル、井上道義とサンクトペテルブルク響によるライブ盤など、日本人による名演も存在します。
これらの個性豊かな演奏を聴き比べることで、この曲の多面的な魅力や指揮者による解釈の違いの面白さを発見することができるでしょう。
時代を超えて響く普遍的な魅力
ショスタコーヴィチの交響曲第5番は、作曲家が置かれた時代の困難や政治的な圧力といった背景から生まれた作品ですが、それだけにとどまらない普遍的な力を持っています。作品に込められたとされる内面の苦悩、絶望、そしてそこから立ち上がろうとする人間の強い意志は、時代や国境を超えて聴く人の心に深く響き、共感を呼び起こします。
この作品には、明確な答えや単一のメッセージがあるわけではありません。聴く人それぞれが、自身の経験や感情と向き合いながら、音楽の中に自分だけの物語や意味を見出すことができる、まさに「オープンな書物」のような作品です。
もちろん、難しい背景や解釈の議論を知らなくても、純粋に音楽として楽しむことも素晴らしいことです。近代的でかっこいいオーケストレーション、心に突き刺さるようなメロディー、そして圧倒的な迫力は、クラシック音楽初心者の方でもきっとその魅力を感じ取れるはずです。

交響曲第5番の定説は、最初が「共産主義革命の勝利」。
次に暴露本「ショスタコーヴィチの証言」が発刊されたことで「強制された歓喜」へと解釈が変わります。ソ連が現存していた当時、日本でもこの本はかなり話題となりました。私も購入したクチです。
そして今日では、不倫相手だったリャーリャに向けたメッセージ、しかもストーカー的要素の多分に強い粘着質なナゾかけがあると判明し、キモいオジサンの音楽になっていきそうです(そうはならんか😅)。
なにしろ一筋縄でいかないのがタコさん(ショスタコーヴィチのマニアの呼称)のねじれた魅力であります。本音と建前が混然一体となって、複雑な味わいを形成しているのです。
今回、同曲をいろいろ聴き比べました。ところがムラさん(ムラヴィンスキーのマニアの呼称)晩年の映像なんか見ちゃうと、やっぱりこれは「革命の勝利」だったのかと圧倒されます。
ソ連という、人類史上2番目(トップは現存する隣国)の規模で大量殺戮を行った「共産主義国家」は、その見返りとして化け物級の指揮者とオケを生み出しました。
ショスタコーヴィチも個人としてはスターリンの犠牲者かもしれませんが、この体制からのみしか生まれなかった彼の音楽を思えば、ことは実に複雑です。

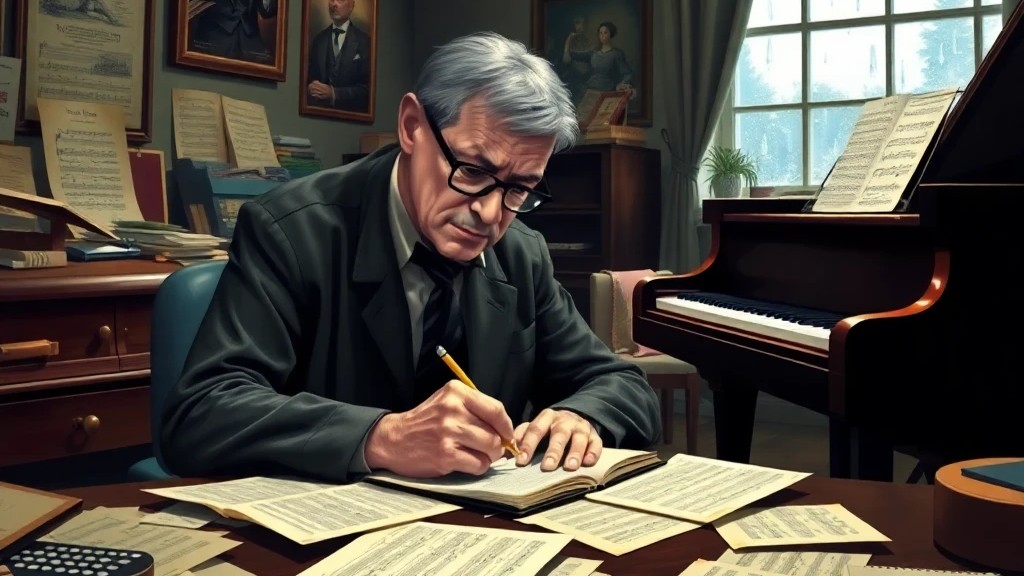
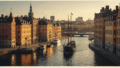

コメント