こども家庭庁は必要?不要?議論の背景と取り組みを徹底解説
2023年4月に「こども家庭庁」が発足しました。子供や家庭を支援するために設立されたこの新しい組織について、「必要だ」「不要だ」といった様々な議論が聞かれます。
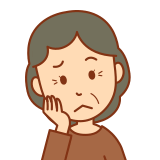
そもそも、どういう組織なのか分らないわ
こども家庭庁がなぜ設立されたのか、どのような活動をしているのか、そしてなぜ議論が起きているのかを分かりやすく解説します。
こども家庭庁設立の背景と目的
こども家庭庁は、子供の健やかな成長を社会全体で支えることを目指して設立されました。その背景には、日本が直面している様々な課題があります。
国際的な視点では、国連で採択された「子どもの権利条約」があります。この条約は、世界中の子供が人間らしく幸せに生き、健康に成長するための「子どもの権利」を定めており、日本を含む多くの国や地域が守ることを約束しています。子どもの権利条約には、命が守られ成長できること、子供にとって最もよいこと、意見を表明し参加できること、差別されないこと、といった4つの原則があります。
日本は1994年に、この条約を守ると約束しました。その後、日本国憲法に基づき子供の権利や人権を守るための法律「こども基本法」が整い、それに合わせてこども家庭庁が発足したのです。こども家庭庁は「こどもまんなか」を理念として掲げています。
日本国内では子どもの貧困、いじめ、虐待、不登校、自殺といった深刻な問題が続いています。近年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、不安や孤立感が増大し、親が子育ての悩みを相談できず虐待の深刻化につながったり、ひとり親家庭の約7人に1人の子どもが貧困状態にあるなど、経済的な困窮も進みました。ネットでの誹謗中傷、いわゆるネットいじめも過去最多となるなど、子供を取り巻く環境は複雑化しています。
これまで子供に関する政策が複数の省庁に分散しており、担当部署や子供の年齢で分断されがちな「縦割り行政」の弊害が指摘されていました。例えば、保育園は厚生労働省、幼稚園は文部科学省、認定こども園は内閣府と管轄が分かれています。このような状況は子供や家庭が抱える複雑な課題に対して、切れ目のない包括的な支援を行うことが難しかったのです。
子ども関連の課題解決への期待を担って、こども家庭庁は誕生しました。こども家庭庁はこれらの課題に対し、司令塔として政策を強力に推進し、縦割り行政を打破して新しい政策課題や隙間事案にも対応することを目指しています。

縦割り行政の打破なんて勇ましいこと言うけど、今までやれたためしないじゃない よほど強力な権限とリーダーシップをもった内閣と担当大臣が就くなくちゃね
巨額な予算と無駄遣い論
こども家庭庁が議論の的となる理由の一つに、その予算規模があります。2025年度の予算は約7.3兆円とされています。この巨額な予算に対して、「無駄遣いではないか」という声も上がっています。
この予算を解体して一人あたりに直接給付すれば、子育てに約900万円使えるのではないかという議論もあります。少子化対策には現状の倍にあたる約14兆円が必要だという意見や、「一人産んだら合計2000万円給付」のように、シンプルな制度にした方が無駄な事務作業や事務員を減らせるという意見もあります。
なぜこれほど複雑な制度になっているのかという疑問に対して、「利権」が関わっている可能性が指摘されています。各分野にまたがる制度設計によって、それぞれの業者が儲かるような横断的な構造になっている、という見方です。
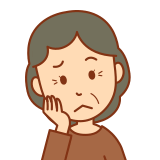
まさにこれ! 国のトップが「日本の財政はギリシア以下」なんて発言していながら、どこからこんなに莫大な予算を新たに捻出できるのよ 子供につける予算は未来への投資になるわけだから、どうしてもやるなら国債にすべきよね
こども家庭庁の主な役割と組織
こども家庭庁の役割は大きく分けて3つあります。
- 様々な省庁が別々に行っていた子供に関する施策を、こども家庭庁がまとめて行うこと。
- 他の省庁で子供に関する施策の動きが十分でない場合、こども家庭庁の大臣は積極的に他の省庁に意見を出したり、働きかけたりすることができる「勧告権」を持つこと。
- 過去に事例がなく解決しなかった問題や担当する省庁がはっきりしなかったことが原因で曖昧になってしまっている課題について、こども家庭庁が取り組むこと。
今まで分散していた子供に対する行政業務や政策を、こども家庭庁が司令塔となることにより、制度や組織などの壁を越えて包括的な支援を実現していくことを目指しています。
施策をスムーズに具現化していくために、こども家庭庁には3つの部門が設けられています。
- 企画立案・総合調整部門 子供の政策を立案したり、各省庁や自治体に働きかけを行ったりする部門です。全体の調整を主な役割とします。
- 成育部門 子供の成長をサポートする部門です。妊娠、出産に関する支援や親と子供の健康支援、保育所や幼稚園など小学校入学前の子供の成長サポート、小中高生の居場所づくり、放課後児童クラブのサポート、子供の安全サポートなどを主な役割とします。
- 支援部門 成長過程で特に支援が必要な子供をサポートする部門です。子供の虐待防止やヤングケアラーなどの支援、血縁関係がない家族と暮らしている子供の生活充実や成人後の自立支援、子供の貧困やひとり親家庭の支援、障害のある子供の支援などを主な役割とします。
こども家庭庁が必要とされる具体的な取り組み
こども家庭庁は、子供や家庭を取り巻く様々な課題に対応するため、多岐にわたる取り組みを進めています。以下にその一部を紹介します。
困難を抱える子どもや家庭を守るための支援に力を入れています。児童虐待の防止、子供自殺対策、そして死亡事例を検証するチャイルドデスレビューなどが挙げられます。教職員向けの研修などを通じて、児童虐待の早期発見と対応の徹底を図っています。また、性的児童虐待の防止に向けた対策や、性被害を受けた子供への専門的なケアと支援も進められています。カルト宗教の二世の虐待問題についても虐待の一類型として重視され、対応が進んでいます。
妊娠期からの切れ目のない支援も重要な取り組みです。特に予期せぬ妊娠をした若年妊婦など、困難を抱えた女性への相談支援や一時的な居場所の確保なども行っています。安心して産科医療を受けられるよう、産科医療補償制度の整備や不妊治療の保険適用なども行われています。
社会的養護が必要な子供への支援も進められています。家庭での養育が困難な子供ができる限り家庭に近い環境で育つことができるよう、里親委託や里親支援の推進に力を入れています。乳児院に預けられている多くの赤ちゃんがいる現状(世界的に見ても少ない)も課題として挙げられています。施設で暮らす子供への学習・進学支援も行われています。
障害のある子供たちへの対応も重要な課題です。医療的ケアが必要な子供や発達障害のある子供への支援、特別支援教育就学奨励費による経済的負担軽減、障害のある子供とない子供が共に学ぶ交流及び共同学習の推進などが行われています。学校での医療的ケアに対応するため、看護職員の配置なども支援しています。障害者手帳の発行や施策が都道府県によって異なり、一貫性がなかった問題にも取り組んでいます。補装具の所得制限の撤廃も議論が進んでいます。
経済的な支援としては、子育て費用に関する給付や、保育無償化、高校生等への奨学金や授業料減免、生活保護世帯の子供への進学支援などがあります。養育費の確保に向けた相談支援や、ひとり親家庭への就労支援なども行われています。児童手当についても、所得制限の撤廃や高校までの延長、多子世帯への支援拡充などが議論され、改革が加えられています。高等教育の修学支援も拡充されています。
仕事と育児の両立支援も進められています。育児休業に関する手当や、男性の育児休業取得促進、両立支援等助成金の支給などが行われています。
子供の意見を政策に反映させる取り組みも始まっています。こども基本法に基づき、子供の権利や政策の利益、子供の意見反映が進んできています。国や地方の審議会などに子供や若者を登用する取り組みも進められています。子供の声を政策づくりのベースにするため、「こども若者★いけんぷらす」という意見表明の機会も設けられています。
その他、いじめ対策、不登校対策、孤独・孤立対策、非行や犯罪に陥った子供の立ち直り支援、小児医療の充実、予防接種、災害時支援、インターネットの適切な利用促進や性被害防止に向けた啓発活動、安全な通学路や公園の整備、文化芸術やスポーツ活動の支援など、非常に多岐にわたる分野で取り組みが行われています。これらの取り組みを支えるために、児童福祉司や心理専門職といった専門人材の育成や研修も強化されています。また、特定の親が働いているかにかかわらず誰でも子供を預けられる「こども誰でも通園制度」の整備も進められています。

あのさ、お題目は立派だけど、今までまるで成果の出なかった課題に誰が取り組むの? まさか、動画でカンペ読んでるこの女の人じゃないよね ものによってはデリケートな心の部分にまで関わることになるけど、そんなことあなたたちに対応可能なの?
こども家庭庁の予算規模
予算規模に対する批判と懸念
こども家庭庁の巨額な予算に対しては、主に以下のような批判や懸念が挙げられています。
- 「お金の無駄ではないか」という意見。ネット上では、この予算を子供1人当たりに換算すると約900万円になり、「生まれたときに900万円を配ってしまえば、こども家庭庁は必要ないのではないか」という声があります。5.3兆円や6.5兆円の予算についても、同様の意見が見られます。
- 他の政策への転用に関する意見。その予算があれば「保育園から大学まで無償にできるのではないか」という意見もあります。
- 「そもそも何をやっているのか分からない」「結果が出ていないのではないか」という声。予算に見合う成果が出ているのか、これから出せるのか、疑問視する意見も見られます。
- 既存政策との重複や複雑化に関する懸念。既にあった政策がほとんどで、事務仕事量を減らして省庁間の連携を強化すれば良いだけで、こども家庭庁を廃止しても問題ないという意見や、「無駄な省庁」が増えることでポストや利権、天下り先が増えるという批判もあります。
- 予算執行の透明性や効率性への疑問。予算はさまざまな部署に二重三重で割り振られていたり、市区町村で類似のサービスが実施されていたりする場合があるとの指摘もあります。特に情報発信に関する予算については、広告代理店への依存や効果検証の不足が「中抜きのような形」で批判される原因になる可能性があります。
- 「子どもを持たない家庭や人にとって無駄ではないか」という意見 も存在します。
- 財源確保の不透明さ。これだけの予算をどのように確保するのかが明確にされておらず、増税の可能性や既存省庁からの予算引きはがしの難しさ、財務省の影響力に関する懸念も指摘されています。
「こども家庭庁を廃止すると勤労者1人につき年間107,000円の減税ができる」という情報がネットで拡散されたことも、「こども家庭庁を廃止したほうがいい」という声が高まる一因となったようです。
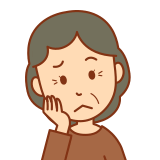
やってることが今までの延長なら、それぞれの省庁から職員を引っ張ってくればいいだけでしょ 理屈からすれば人件費は据え置きになるはずだし、運営管理も各省庁が割合で負担すればいいだけ それをまるまる新しい予算でやるなんて、デタラメ過ぎない?
予算の内訳と検証の必要性
情報発信に関する費用やEBPM(証拠に基づく政策立案)事業などが関連予算として挙げられています。EBPMについては、予算が効果的に使われているかを検証する必要があるものの、まだ始まったばかりで十分ではないという声もあります。概算要求の金額も大きく、その中身を詳しく見ていく必要があると指摘されています。
必要性との議論の背景
これらの批判がある一方で、こども家庭庁が必要だとされる背景には、日本が直面している少子化の加速、子供の問題の複雑化、そしてこれまでの縦割り行政の弊害を解消し、子供政策を統合的に推進する必要性があることが挙げられます。子供の貧困、いじめ、虐待といった問題が深刻化しており、これらの課題に対して、従来の省庁の枠を超えた対応が求められているのです。
こども家庭庁の予算規模に対する批判は根強く存在しますが、その一方で、子供を取り巻く喫緊の課題に対応し、「こどもまんなか社会」を実現するためには、適切な予算とそれを効果的に執行する仕組みが不可欠であると言えます。今後の予算の使われ方や、具体的な成果が検証されていくことが重要です。
課題と批判の背景にあるもの
こども家庭庁には、先に述べた予算の無駄遣い懸念や利権構造の指摘の他に、具体的な課題も指摘されています。
設立の提唱者からも、今のこども家庭庁が抱える問題や課題が挙げられています。例えば、困難を抱える子供や家庭への対応が十分ではない、医療的ケア児や発達障害の子供への対応ができていない、といった指摘があります。乳児院に多くの子供たちがいる現状も、世界的に見て少ないと言われており、改善が進んでいない課題です。
EBPM(証拠に基づく政策立案)についても検証が始まったばかりで、まだ十分ではないという声もあります。文化立国を目指す上で重要なコンテンツ産業への支援予算が、財務省の査定で認められにくい現状があり、財務省がコンテンツ産業を子供の遊びのように考えているのではないかという危惧も示されています。
政治が子供に無関心であるという批判もあります。異次元の少子化対策と言われる政策が、本当に子供の最善の利益を追求しているのか、こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか社会」に本当に子供がいるのか、疑問が投げかけられています。こども家庭庁の目指すものが少子化対策と誤解されている現状があるという指摘もあります。

聞こえばかりいい言葉と、聞き慣れない単語の羅列ばかり まるで心に響かないのは、お役所文章の典型だな 「問題があるから解決しよう」じゃなくて、「問題をこさえてカネや省益にしよう」としか読めないんだけど
また、縦割り行政の解消を目指したにもかかわらず、文部科学省が管轄する幼稚園との連携にとどまり、幼保一元化が見送られた点も課題として挙げられています。これにより、教育と福祉の連携が不十分になる懸念が指摘されています。各省庁への勧告権が与えられていますが、強制力がないため、実際に他の省庁の協力が得られるかどうかが懸念されています。デジタル庁の例を引き合いに出し、出身省庁の意向が強く働き、組織がうまくまとまらない可能性も指摘されています。
予算の確保についても課題であり、財源をどのように確保するのかが明確になっていない点も懸念材料です。
「こども家庭庁」という名称についても、「家庭」という言葉が入ることで、問題を解決するのは最終的に家庭である、という印象を与えてしまうという指摘もあります。
現場からは、子どもの居場所事業などが学童保育と混同され、予算化・制度化されにくい現状や、専門的な知識を持った担い手の確保・育成の難しさも課題として挙げられています。
今後の展望
こども家庭庁は設立されたばかりの新しい組織であり、今後その活動がさらに進められていくことになります。
こども基本法の理念に基づき、子どもの意見をしっかりと聞き、政策に反映させる仕組みづくりは始まったばかりです。EBPMを推進し、施策がどれだけ進んだのか、予算が効果的に使われているのかを検証していく厳しいチェックが必要です。
困難を抱える子供や家庭への支援、社会的養護の推進、医療的ケア児や障害児への対応など、具体的な課題への取り組みを一層進めていくことが求められています。予算の効率的な執行と、支援が必要な子供や家庭に確実に届くような制度設計も、引き続き重要な課題となるでしょう。自治体間の格差をなくし、命に関わる基盤的なサービスに関しては差があってはならないという点も重要です。プッシュ型の支援に移行し、情報連携のDX化を進める必要性も指摘されています。
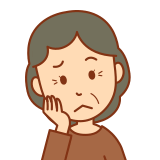
子ども・子育て支援金制度って、再エネ賦課金の時と手口がまるで一緒ね 実質は増税と変わらないんだけど、最初は単価を低く設定して、10年後には一けた大きい額にまで上げていく もうね、国民は余裕どころか毎日の食事にさえ困っているのに、とれる機会があればどんどん取ってやれって姿勢のままなのよね 増税増税で若い人はますます家庭を持てなくなるし、少子化加速制度としか思えないわ
まとめ
こども家庭庁の必要性や不要性については様々な意見がありますが、その設立の背景には子供を取り巻く深刻な社会課題と、子供の権利を守り健やかな成長を支えるという重要な目的があります。
約7.3兆円という予算には無駄遣いを懸念する声もありますが、子供や家庭を支援するための具体的な取り組みは多岐にわたります。一方で、困難を抱える子供への対応の遅れや、乳児院の問題、幼保一元化の見送りなど、解決すべき課題も多く残されています。
こども家庭庁が掲げる「こどもまんなか」の理念を実現し、全ての子供たちが安心して成長できる社会を築いていくためには、その活動をしっかりと見守り、効果を検証し、必要に応じて改善を求めていくことが私たち一人ひとりに求められます。こども家庭庁が必要かどうかを決めるのは、この庁を問題解決に向かわせる努力と、国民が課題を理解することにかかっています。

最後にこの動画見ると、腹立つわ~

子供(ひらがなの「こども」や「子ども」を使う明確な理由が分からないため、旧来の漢字を使用します)に対するいじめや虐待、貧困に対して「対処療法」を施そうというのが、こども家庭庁になります。
ではなぜ、年々そうした諸問題が深刻化し、国民の莫大な血税をつぎ込まなければならない事態に陥ったのか。
歴代の少子化担当大臣が代わるたび、少子化はかえって進み、貧困も虐待も顕在化していきます。つまり過去の政策は、ことごとく失敗であったということです。そしてそのことに対し、責任を取った政治家や官僚、知識人は存在しません。
根本の原因がなんであるかの考察なしに、新たな組織など作っても意味がないと、誰しもが思うでしょう。
いったい誰が、日本を貧しくしているのでしょうか。まさか「自己責任」とばかり責任転嫁は出来ないはずです。日本人の勤勉さ、他者を思いやる心、仕事に対する責任感の強さは、今も昔も変わりません。もはや答えは明白であり、その悪しき要素を取り除けば、日本は今よりよほど豊かになるはずです。
自分や家族、地域や国に対して矜持と尊敬の念があれば、我が子を虐待する親は減るでしょうし、他者をイジメる気持ちなど起きにくくなります。
なにより「お母さん」という、人類にとって最も尊い存在を軽んじ、社会に出て働く女性を上位に置く風潮が改まらない限り、少子化問題が解決するはずなどありません。
真っ当な教育を理解しない国家がいくらカネ(国民の血税)ばかりつぎ込もうと、今後も問題は悪化の一途をたどるでしょう。こども家庭庁は不要であるどころか、日本の未来を危うくしているのではないでしょうか。
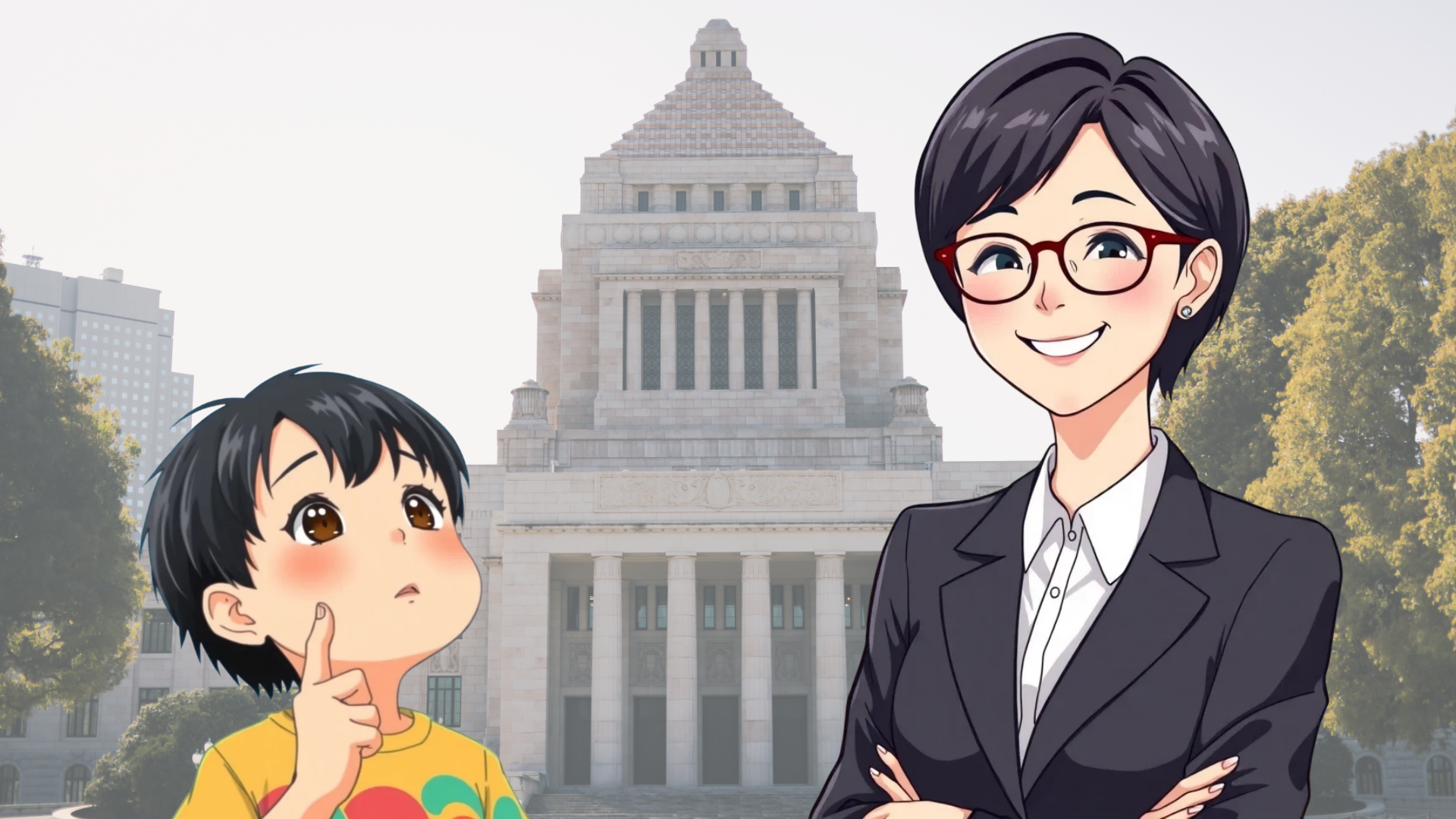


コメント