グリーグの「朝」
グリーグの『ペール・ギュント』第1組曲 作品46の冒頭を飾る「朝(Morgenstemning)」は有名な楽曲であり、その穏やかで美しい旋律は多くの人々に親しまれています。イプセンの戯曲『ペール・ギュント』の第4幕への前奏曲として作曲されました。
楽曲の背景(戯曲における位置づけ)
戯曲の第4幕は、ペール・ギュントが長年の放浪生活を経て、モロッコの海岸で目を覚ます場面から始まります。彼はかつての財産を失い、一人寂しく朝を迎えます。この音楽は、異国の地・北アフリカの広大な砂漠やそこに昇る朝日、そしてペールの孤独な心象風景を描写しています。
音楽的特徴
- 穏やかで瞑想的な雰囲気: 全体を通して、静かで落ち着いた雰囲気が漂っています。冒頭のフルートとオーボエによるユニゾン(同じ旋律を同じ高さで演奏すること)は、広大な自然の静けさや、ゆっくりと訪れる朝の光を感じさせます。
- 美しい旋律: 覚えやすく、心に深く染み入るような美しい旋律が特徴です。この旋律は曲全体を通して様々な楽器に受け継がれ、展開していきます。
- 徐々に高まる感情: 曲は静かに始まりますが、次第に楽器が増え、音量もクレッシェンド(だんだん強く)していきます。これにより、朝日の力強さやペールの内面に湧き上がる感情の動きが表現されていきます。
- 色彩豊かなオーケストレーション: フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットといった木管楽器が中心となり、清涼感のある音色を作り出しています。ホルンや弦楽器も加わり、豊かなハーモニーを奏でます。
- 北欧的な憂い: 美しい旋律の中にもどこか物憂い、郷愁を誘う北欧的な情感が感じられます。これは故郷を遠く離れ、孤独なペールの心情を反映しているとも考えられます。
- 単純な構成: 比較的単純な構成でありながら、その旋律の美しさとオーケストレーションの妙によって、聴く者の心に深く残る印象的な楽曲となっています。
楽曲が表現するもの(一般的な解釈)
- 朝の情景: 昇りゆく朝日、静寂に包まれた風景、徐々に活気づく自然の様子などが目に浮かぶようです。
- 異国情緒: 北アフリカの独特な雰囲気、異文化への憧憬や孤独感などが感じられます。
- ペールの心情: 長い放浪の末の孤独、過去への郷愁、そして未来への漠然とした思いなど、複雑な感情が表現されています。
- 普遍的な感情: 特定の場面だけでなく、希望や安らぎ、そしてほのかな寂しさといった感情を呼び起こします。
「朝」は、その美しい旋律と穏やかな雰囲気から、クラシック音楽に詳しくない人にも親しみやすい楽曲として愛されています。単に美しいだけでなく、戯曲の背景やペールの心情を理解することで、より深くこの音楽の魅力を味わうことができるでしょう。
イプセンの戯曲『ペール・ギュント』
ヘンリック・イプセンの戯曲『ペール・ギュント』は、1867年に発表された壮大な詩劇です。ノルウェーの民話や伝説を下敷きに、主人公ペール・ギュントの波瀾万丈な生涯を通して、人間の本質や生き方、そしてノルウェーの国民性を深く掘り下げた作品です。単なる冒険譚や道徳劇として捉えるよりも、多層的な解釈が可能なイプセンの代表作の一つと言えるでしょう。
詩劇という形式と特徴
『ペール・ギュント』は散文劇が主流だった当時の演劇界において、特異な存在です。全編が韻を踏んだ詩で書かれており、幻想的で自由奔放な世界観を表現するのに大きく貢献しています。場面転換も多く、時間や空間を自在に飛び越えるような構成は、舞台上演だけでなく読み物としても魅力的な作品です。
多層的なテーマ
この戯曲は、以下のような多岐にわたるテーマを内包しています。
- 自己の探求と喪失: ペールは生涯を通じて「自分自身」であろうとしますが、その過程で様々な役割を演じ、本質を見失っていきます。「自分とは何か」という根源的な問いの投げかけは、現代にも通じる普遍的なテーマです。
- ノルウェーの国民性とアイデンティティ: ペールの性格や行動、そして彼が出会う様々な人々を通して、当時のノルウェーの国民性や文化、精神性が風刺的に描かれています。特に現実逃避や誇大妄想といった、国民的な傾向が指摘されています。
- 現実と幻想の曖昧さ: 劇中では、ペールの妄想と夢が現実に入り混じり、観客や読者を翻弄します。この曖昧さによって、人間の内面世界や主観的な現実の重要性が示唆されます。
- 愛と救済: ペールを生涯一途に待ち続けたソルヴェイグの無償の愛は、この劇における重要な要素です。彼女の愛は自己を見失ったペールにとって最後の救いとなったのか、あるいは別の解釈も可能なのか、議論の余地を残しています。
- 罪と赦し: ペールは多くの過ちを犯しますが、彼の罪は単純な道徳的な裁きを受けるものではありません。彼の生き方そのものが問い直され、赦しの意味も深く掘り下げられます。
- 社会批判と風刺: 当時の社会や人間の欺瞞性、功利主義などが、ペールの行動や彼が出会う人々を通して辛辣に批判・風刺されています。
主要な登場人物とその象徴性:
- ペール・ギュント: 夢想家でほら吹き。行動力はあるものの、現実から逃避しがちな主人公です。彼の遍歴は、人間の様々な側面と生き方を象徴的に示しています。
- オーセ: ペールの母。息子に期待を抱きつつも、彼の空想癖に悩まされる複雑な母親像です。
- ソルヴェイグ: ペールを一途に愛し続ける女性。純粋さと献身の象徴であり、ペールにとっての良心や救済の象徴とも解釈できます。
- トロールの王: 独自の価値観を持つトロール社会の支配者。「己にとって十分であれ」という言葉は、人間社会のあり方に対する問いかけとも受け取れます。
- ボイグ: 実体のない謎の存在。「回り道を行け」という言葉は、ペールの生き方を象徴する重要なキーワードとなります。
- ボタン鋳造職人: ペールの魂を審判する存在。彼の言葉は、ペールの人生の意味を問い直す役割を果たします。
あらすじ
第一幕:故郷での騒動と逃避
放蕩な父を持つペールは、空想にふけり、現実離れしたほらを吹いて母オーセを困らせています。彼はかつて縁談を壊した金持ちの娘イングリードの結婚式に乗り込み、周囲の嘲笑を浴びながらも彼女を強引に連れ去り、山中で一夜を過ごします。この行動により、ペールは故郷から追放されることになりました。第一幕では、ペールの奔放な性格、周囲との軋轢、そして現実から逃避する傾向が描かれます。
第二幕:山中での幻想と自己との乖離
山中を彷徨うペールは、トロールに求愛されるのを待つ娘たちと出会い、幻想的な体験をします。彼はトロールの王の娘と出会い、トロールになる誘いを受けますが、これを拒否。しかし彼女は、ペールの「頭の中」で子供を宿したと告げられます。ここで重要なのは、トロールの「己にとって十分であれ」という利己的なモットーと、実体のない存在ボイグの「回り道を行け」という言葉です。これらの出会いはペールが自己中心的になり、真実から目を背ける生き方を選ぶ伏線となります。目を覚ましたペールは、ソルヴェイグの妹ヘルガから彼女の伝言と贈り物を託されますが、再び逃避の旅に出ます。
第三幕:ソルヴェイグとの出会いと別れ
山小屋を建てて生活を始めたペールの元に、彼を慕うソルヴェイグが現れ、共に生きることを選びます。しかし、かつてペールが関わった緑色の服の女が現れ、ペールの過去の行いを突きつけます。過去の罪とソルヴェイグへの罪悪感に苛まれたペールは、「回り道を行け」という声に導かれるように、ソルヴェイグを残して再び旅に出ます。彼は母オーセの臨終に一時帰郷しますが、すぐにまた海外へと向かいます。
第四幕:海外での成功と空虚
長く海外で様々な役割を演じたペールの姿が描かれます。彼はモロッコの商人として非倫理的な取引を行い、預言者として祭り上げられ、歴史家としても活動します。一時は富と名声を手に入れますが、それは表面的で空虚なものでした。精神病院では「自己」の皇帝として迎えられるものの、彼は自己中心的な生き方の行き詰まりを感じ、絶望します。この幕では、ペールの外面的な成功と内面的な空虚さのギャップが際立ちます。
第五幕:帰郷と魂の審判
老いたペールは難破し、故郷に戻ります。彼は過去の自分の痕跡を辿りながら、自分が本当に生きてこなかったという感覚に苛まれます。ボタン鋳造職人が現れ、ペールが「自分自身」として生きた瞬間を示すことができなければ、彼の魂を溶かすと宣告します。トロールの王は、ペールは人間ではなくトロールとして生きてきたと主張。悪魔さえも、ペールは重大な罪を犯していないと言います。
絶望するペールですが、彼を待ち続けたソルヴェイグの深い愛に触れ、「あなたは何も罪を犯していません」という言葉に救いを求めます。ソルヴェイグの子守唄を聞きながら、ペールは安らかな死を迎えるようにも見えますが、ボタン鋳造職人は最後の審判がまだ終わっていないことを示唆して幕を閉じます。第五幕ではペールの人生の総括と、愛による救済の可能性、そして自己の探求の難しさが描かれます。
ペール・ギュントの人物像
イプセンが戯曲『ペール・ギュント』を通して描こうとしたペール・ギュントの人物像は、非常に多面的で捉えどころがなく、解釈の幅が広いのが特徴です。単に「良い人」「悪い人」といった単純な二元論では語れない、複雑で人間的な存在として描かれています。
イプセンはペール・ギュントという特異な人物を通して、人間の普遍的な弱さや矛盾、そして自己探求の難しさを描こうとしました。ペールの極端な行動や性格は、誇張されているとはいえ、私たち自身の内面に潜む可能性や傾向を映し出していると言えるでしょう。
当時のノルウェー社会や国民性に対する、批判的な視点も込められていると考えられます。現実から目を背け、誇大妄想に陥りがちな国民性や、表面的な成功や役割に囚われがちな人間の姿を、ペールを通して風刺的に描いたとも解釈できます。
最終的にペール・ギュントが「自分自身」を見つけることができたのかどうかは、解釈が分かれるところです。ソルヴェイグの無償の愛によって救済されたと見ることもできますが、彼の自己探求の旅は未完のまま終わったと捉えることもできます。
イプセンはペール・ギュントという複雑な人物像を通して、観客や読者に「自分とは何か」「いかに生きるべきか」という根源的な問いを投げかけ、それぞれの解釈を促していると言えるでしょう。
組曲版『ペール・ギュント』
グリーグは、この劇付随音楽の中から特に人気のある楽曲を選び、2つの管弦楽組曲として再構成しました。これにより劇を観ていない人でも、グリーグの美しい音楽に触れる機会が広まりました。組曲版は演奏会でも頻繁に演奏され、グリーグの代表作として世界中で愛されています。
グリーグの『ペール・ギュント』は、イプセンの文学的な世界観を見事に音楽で表現した傑作であり、北欧の豊かな自然や人々の感情、そして幻想的な雰囲気を色彩豊かに描き出しています。

イプセンは叙情的な叙事詩を書きながら、「近代演劇の父」であり、演劇リアリズムの先駆者でもありました。人間の多面性や複雑さを表すのに、彼と演劇は最適な組み合わせだったでしょう。
一方、それに付帯する『ペール・ギュント』の音楽は、戯曲の中身さえ知らなければ実に美しく、素朴にさえ響きます。
このあたりが文字に始まる具象の表現と、音符の解釈から生まれる抽象的な表現との差かもしれません。
イプセンの戯曲は人に「なぜ?」を突きつけますが、グリーグの音楽は何も強いたりしません。そして今『ペール・ギュント』といえば、断ぜん後者なのです。

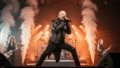

コメント