1960年、若き日の天才トランペッター、フレディ・ハバードが世に送り出したデビューアルバム「オープンセサミ」。1960年6月19日にニュージャージー州のルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオで録音され、同年ブルーノート・レコードからリリースされました。当時22歳だったハバードの才能が早くも開花しており、ハード・バップとモーダル・ジャズの要素を融合させた意欲的な作品として評価されています。
参加ミュージシャン
この記念すべきデビュー作には、以下の素晴らしいミュージシャンたちが参加しています。
- フレディ・ハバード (Freddie Hubbard): トランペット
- ティナ・ブルックス (Tina Brooks): テナーサックス
- マッコイ・タイナー (McCoy Tyner): ピアノ
- サム・ジョーンズ (Sam Jones): ベース
- クリフォード・ジャーヴィス (Clifford Jarvis): ドラム
マッコイ・タイナーはこの数ヶ月後、ジョン・コルトレーンのカルテットに加入することになります。
アルバムの特徴と評価
「オープンセサミ」は、フレディ・ハバードの力強く輝かしいトランペットの音色と、驚異的なテクニックが早くも確立されていることを示しています。ハード・バップの推進力とモーダルな響きが融合した、若々しいエネルギーに満ちた演奏が魅力です。
- 「Open Sesame」: ティナ・ブルックスの作曲で、ラテンのリズムと覚えやすいメロディが印象的なハード・バップ・チューンです。ハバードとブルックスのソロが熱く、互いを引き立てています。
- 「But Beautiful」: バラードでの演奏にも、若さの中に深い情感と成熟を感じさせます。
- 「Gypsy Blue」: ブルースフィーリング溢れるブルックスのオリジナルで、ハバードのソロも素晴らしいものです。
- 「All or Nothing at All」: スインギーでドライビングな演奏が展開されます。
- 「One Mint Julep」: R&Bの影響を感じさせるクールなアレンジが施されています。
- 「Hub’s Nub」: ハバード自身の作曲で、複雑なメロディを持つ意欲的な楽曲です。
批評家からの評価も高く、オールミュージックでは4.5つ星を獲得し、「偉大なブルーノートのセット」と評されています。ペンギン・ガイド・トゥ・ジャズでも「コア・コレクション」の一つに選ばれています。
このアルバムはフレディ・ハバードの輝かしいキャリアの始まりを告げる重要な作品であり、1960年代のハード・バップを代表する一枚として、今なお多くのジャズファンに愛聴されています。ティナ・ブルックスの作曲と演奏、そしてマッコイ・タイナーの参加も、このアルバムの価値を高めています。
タイトル曲「Open Sesame」の構成と特徴
タイトル曲である「Open Sesame」は、ラテンのリズムを取り入れたエキゾチックで勢いのあるハード・バップ・チューンです。
- ラテンのリズム: 冒頭から印象的なのは、ファンキーで跳ねるようなラテンのリズムです。このリズムが楽曲全体に独特のグルーヴ感と高揚感を与えています。サム・ジョーンズの力強いベースラインとクリフォード・ジャーヴィスの切れ味鋭いドラムが、このリズムセクションを支えています。
- 覚えやすいメロディ: メインテーマは、一度聴いたら耳に残るキャッチーなメロディを持っています。フレディ・ハバードの明るく力強いトランペットの音色によって、このメロディが鮮やかに際立ちます。
- 熱いソロ展開: 曲の中盤では、フレディ・ハバードとティナ・ブルックスによるソロが繰り広げられます。
- フレディ・ハバードのソロ: 若々しいエネルギーと卓越したテクニックが炸裂します。高音域を駆使した華やかなフレーズや、ブルージーなニュアンスを織り交ぜた表現力豊かなソロは、聴く者を圧倒します。彼の後のキャリアを予感させる、才能の片鱗が早くも感じられます。
- ティナ・ブルックスのソロ: ブルース特有の粘り気と、ハード・バップの力強さを兼ね備えた彼のテナーサックスの音色は、ハバードのトランペットとは異なる魅力を持っています。流麗でありながらも、感情豊かなフレーズが印象的です。
- ピアノソロ: マッコイ・タイナーによるピアノソロも、楽曲に深みと彩りを加えています。彼の独特のハーモニー感覚とリズミカルなアプローチが、楽曲にモーダルな響きを与えています。
- アンサンブルの妙: ソロとソロの間には、テーマが再び演奏され、楽曲全体の構成を引き締めています。ハバードとブルックスのユニゾンやハーモニーも聴きどころの一つです。
- フェードアウト: 曲は熱気を帯びたまま、フェードアウトで終わります。
楽曲が持つ意味合い
タイトルが「Open Sesame(開けゴマ)」であることには、いくつかの解釈が考えられます。
- 未知の扉を開く: デビューアルバムのオープニングを飾るこの曲が、「新たな才能の扉を開く」というハバード自身の未来への期待や決意を表していると解釈できます。
- エキゾチックな雰囲気: ラテンのリズムが持つエキゾチックな雰囲気と、「開けゴマ」という呪文のイメージが結びつき、聴く者を異世界へと誘うような感覚を与えるのかもしれません。
- ブルックスの意図: 作曲者であるティナ・ブルックスが、どのような意図でこのタイトルを付けたのかは定かではありませんが、楽曲の持つ神秘的で力強いイメージに合致していると言えるでしょう。
後世への影響
「Open Sesame」はフレディ・ハバードの代表的な楽曲の一つとして、多くのジャズミュージシャンに演奏され、影響を与えてきました。そのエネルギッシュな演奏とラテンのリズムを取り入れた斬新なアプローチは、1960年代以降のジャズの多様性を示す好例と言えるでしょう。
この曲を聴くことで、若き日のフレディ・ハバードの才能、そして彼を取り巻く素晴らしいミュージシャンたちの熱演を堪能することができます。まさに、彼の音楽キャリアの扉を開いた、記念すべき一曲と言えるでしょう。
「Open Sesame(開けゴマ)」とは、そもそも何か
「開けゴマ」は、魔法の呪文のように聞こえますよね。この言葉は『アリババと四十人の盗賊』に登場します。物語の中ではアリババが盗賊たちの隠れ家を見つけ、彼らが「開けゴマ!」と唱えて洞窟の扉を開閉するのを目撃します。その後、アリババもこの言葉を唱えて洞窟に入り、宝物を見つけるという展開になります。
『アリババと四十人の盗賊』は『アラビアンナイト(千夜一夜物語)』の中の一編とされていますが、実は原本には収録されていません。イスラム世界に伝わっている物語だそうです。

なぜ「ゴマ」という言葉が選ばれたのかについては、いくつかの説があります。
ゴマの殻が割れる様子からの連想
最も有力な説の一つは、ゴマの種子が成熟するとその小さな殻がパチンと音を立てて開く様子から来たものです。この自然な現象が、固く閉ざされた洞窟の扉が魔法の力で開くイメージと重ね合わされたと考えられています。「開けゴマ!」という呪文は、ゴマの殻が開くように扉も開いてほしいという願いが込められているのかもしれません。
中東におけるゴマの重要性
ゴマは物語の舞台である中東地域において古くから重要な食物であり、油としても貴重なものでした。そのため盗賊たちが隠し持つほどの貴重な宝物と、同じように価値のあるゴマを結びつけたという考え方があります。つまり「ゴマ」は単なる植物の名前ではなく、「貴重なもの」「富」の象徴として用いられたという解釈です。
言葉の響きや象徴性
「開けゴマ」という言葉の響き自体が、どこか神秘的で、魔法のような印象を与えるという側面も考えられます。「ゴマ」という音の繰り返しが、呪文としての効果を高めているのかもしれません。また、ゴマの小さな粒が集まって大きな力を持つように、この呪文も小さな言葉の中に大きな力を秘めている、という象徴的な意味合いも考えられます。
言語学的な背景
アラビア語でゴマは「simsim(سمسم)」と言います。この言葉の響き自体に、古代の人々が何らかの神秘的な力を感じていた可能性が指摘されています。
これらの説が複合的に作用して、「開けゴマ」という呪文が生まれたのかもしれません。物語の作者がゴマの持つ自然な特性や文化的な背景、言葉の響きなどを巧みに利用して、この印象的な呪文を作り上げたと言えるでしょう。
どの説が最も有力であるかは断定できませんが、それぞれの説が「開けゴマ」という言葉の背後にある豊かな意味合いを示唆していますね。
世界の「Open Sesame(開けゴマ)」
クール・アンド・ザ・ギャングが1976年に発表した、同名のアルバムのために録音した曲です。
スウェーデンのユーロダンスアーティスト、Leila Kの曲で、1992年10月にComaレーベルから2枚目のアルバム「Carousel」のリードシングルとしてリリースされました。いかにも呪文っぽいですね。
パワーメタルバンドエドガイ(EDGUY)の「Open Sesame」はキャッチーで、ライブでも盛り上がる人気曲の一つとして知られています。スコーピオンズみたいと思ったら、やっぱりドイツだった。

フレディ・ハバードはときとして、あまりの上手さが鼻についたりもします。「どうだ、他の奴らじゃここまで出来ねぇだろ」みたいに聴こえちゃう瞬間が、どうしてもあるんですね。
ところがこのデビュー盤に限っては、実に素直に「いいなぁ、スゲ〜な」と楽しめます。響きがとても新鮮だし、音もつき抜けてるし、あまり取り上げられないけどジャズのビギナー向けに最適じゃないかと、個人的には思っています。
「開けゴマ」のイメージにぴったりな表題曲。重すぎず軽すぎず、聴けば自然に体が揺れてきます。

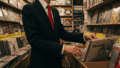

コメント